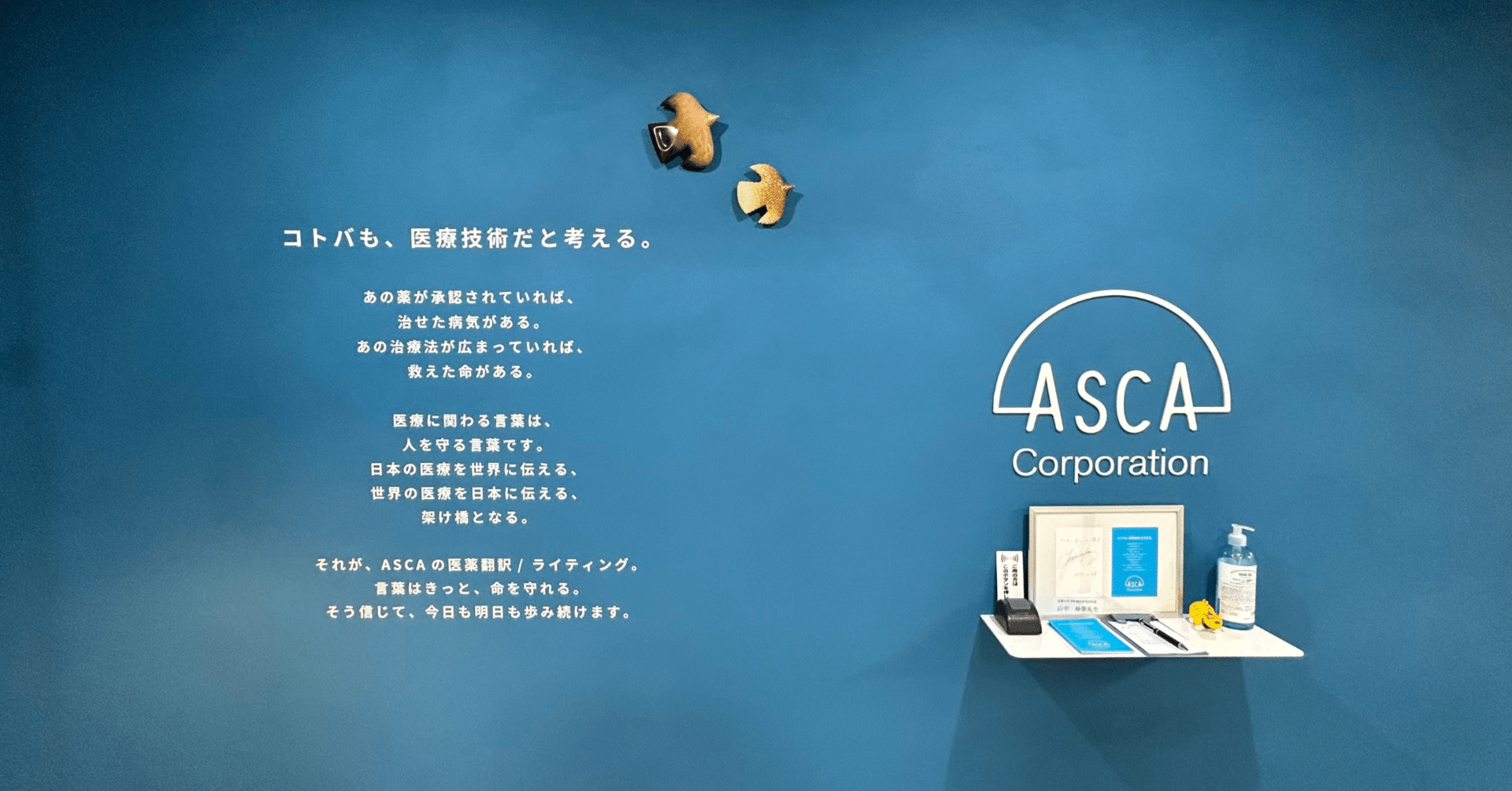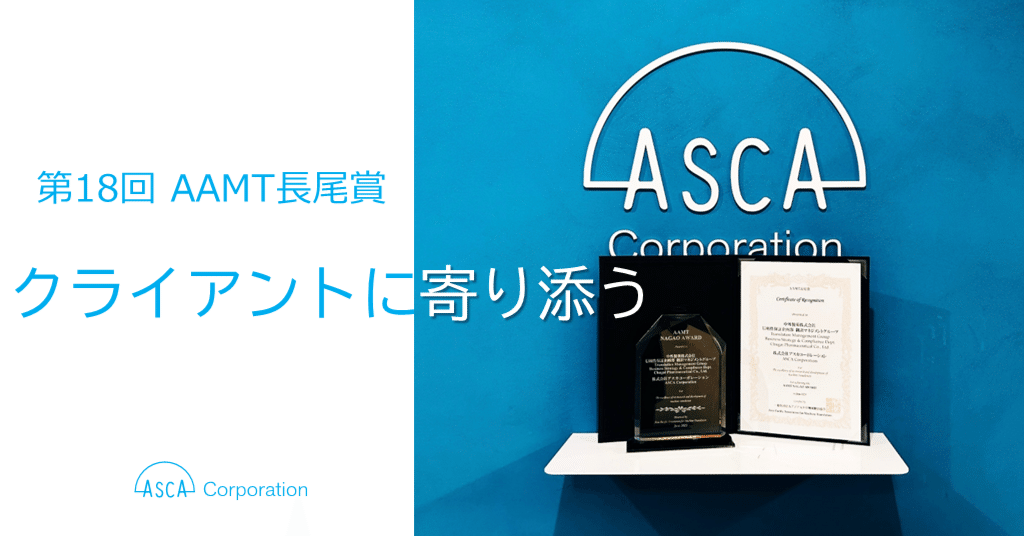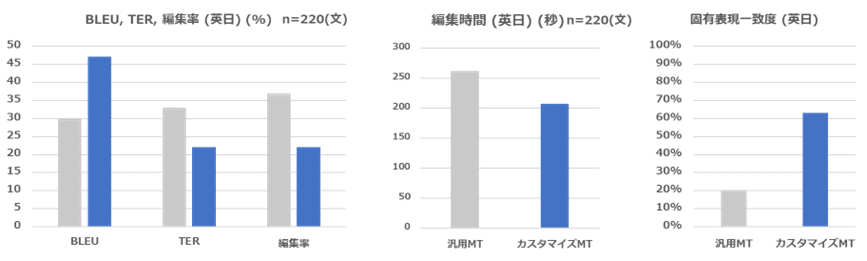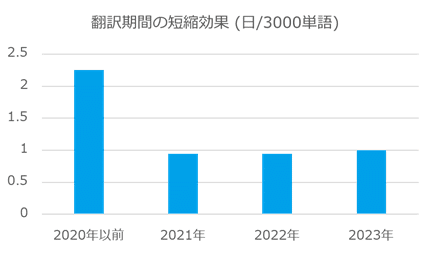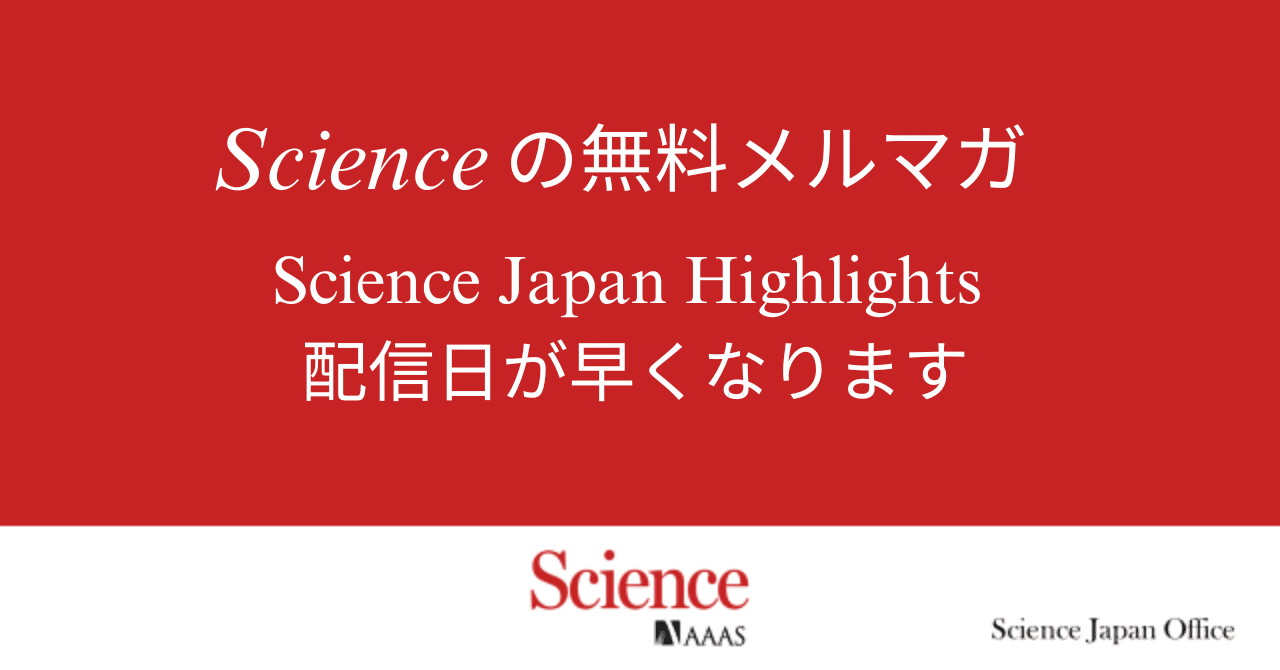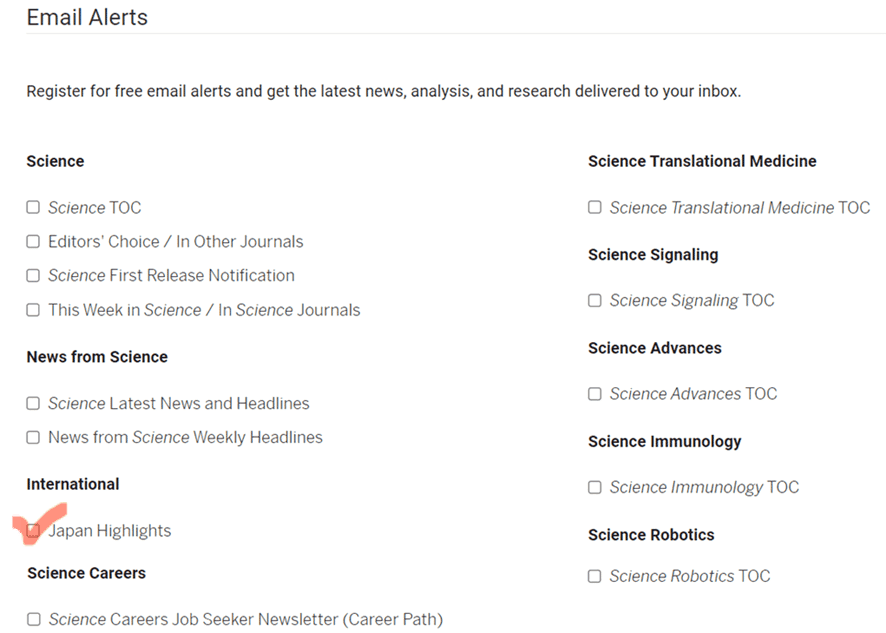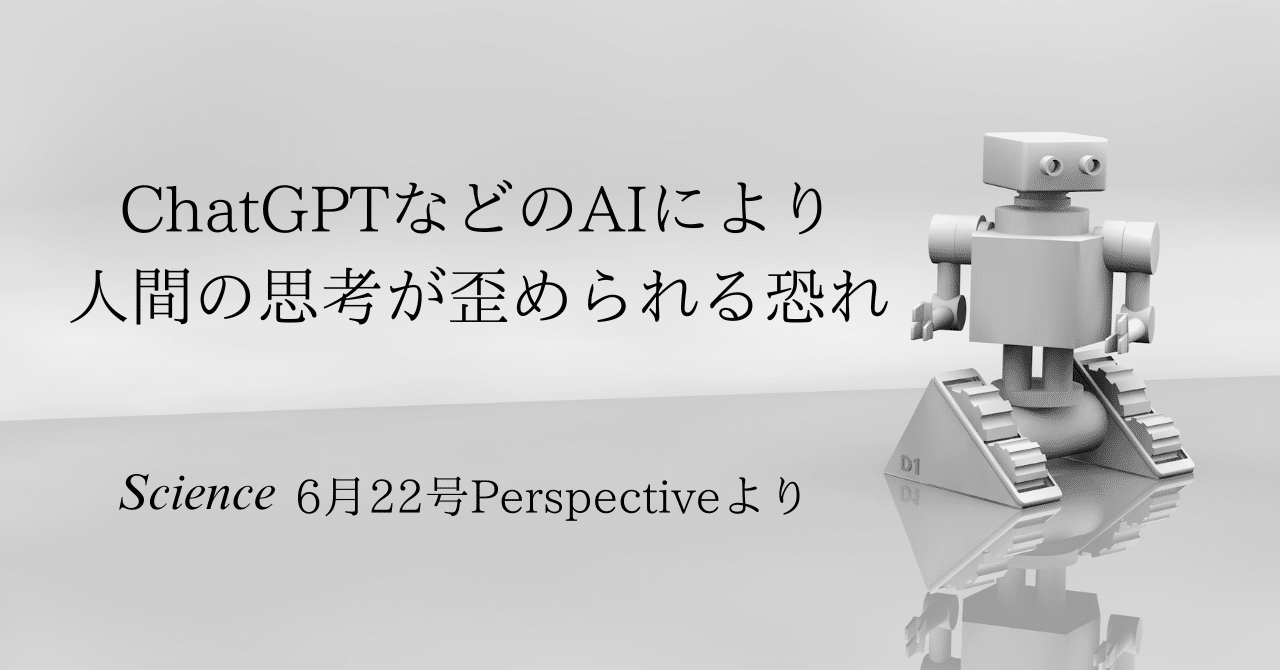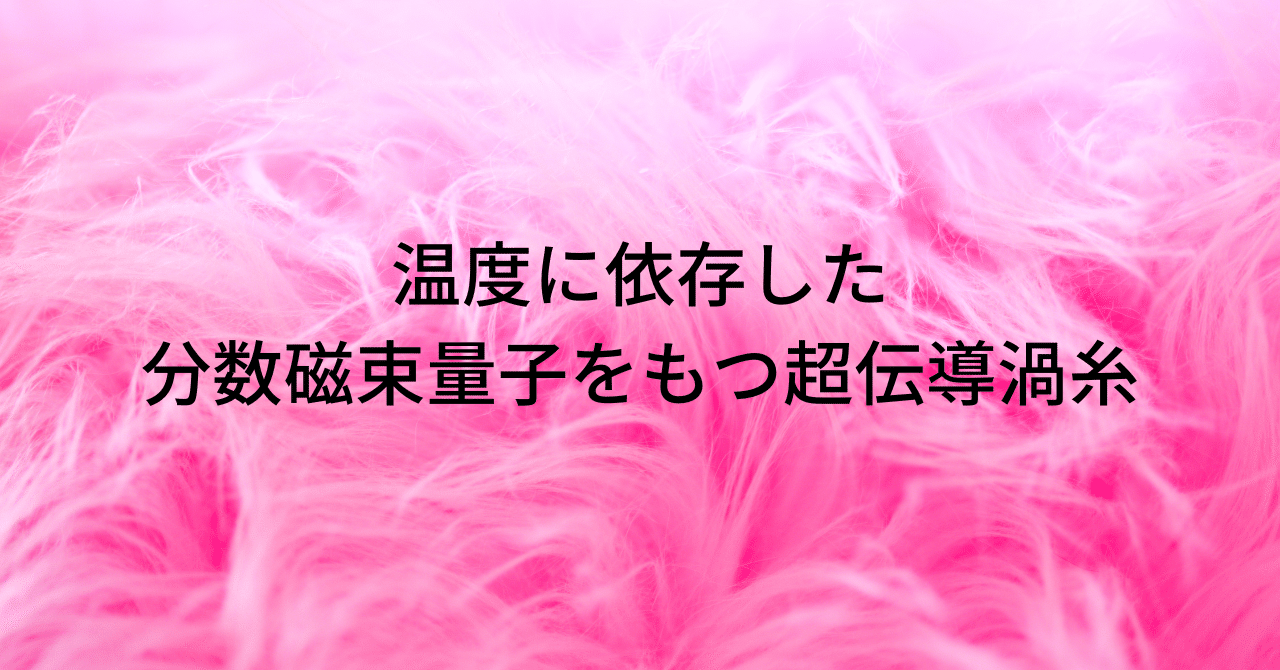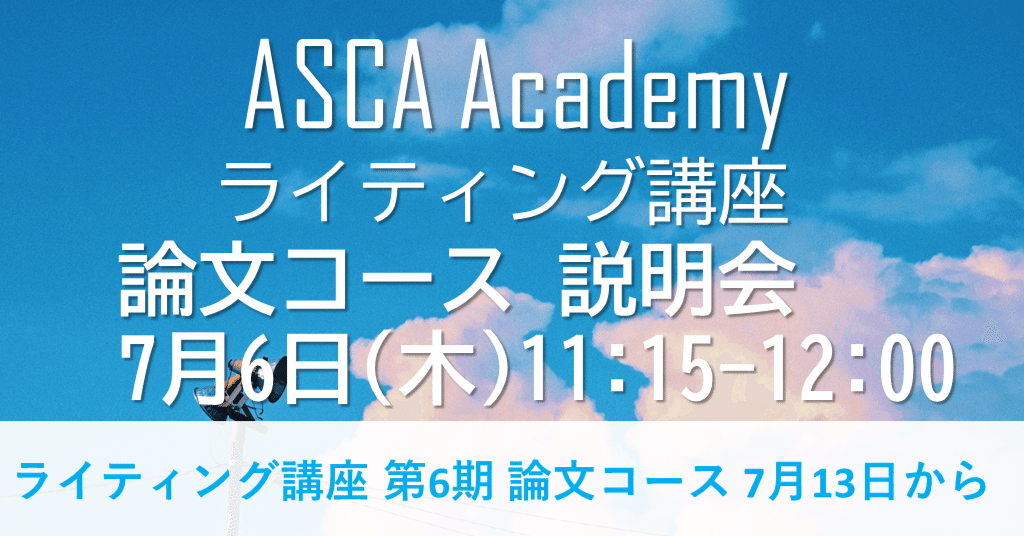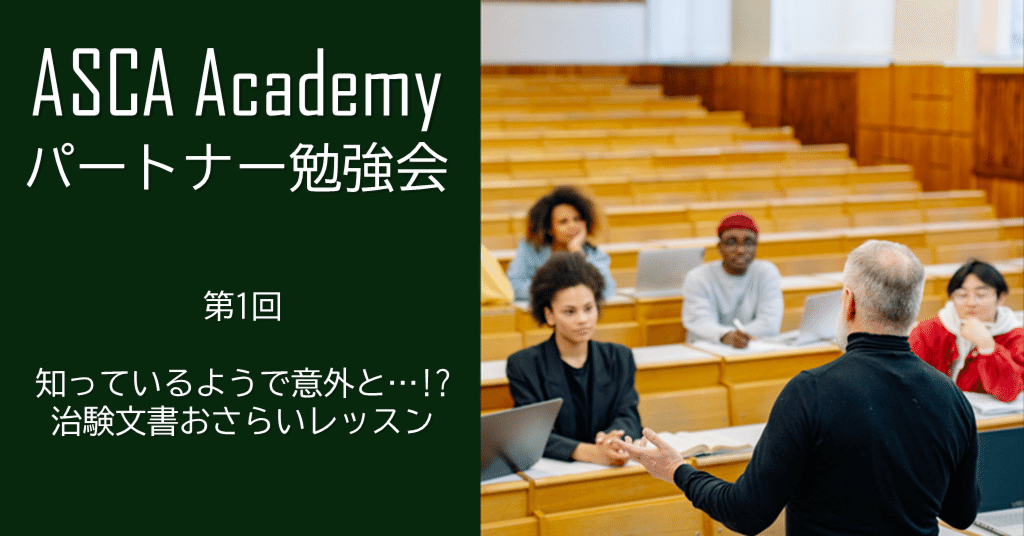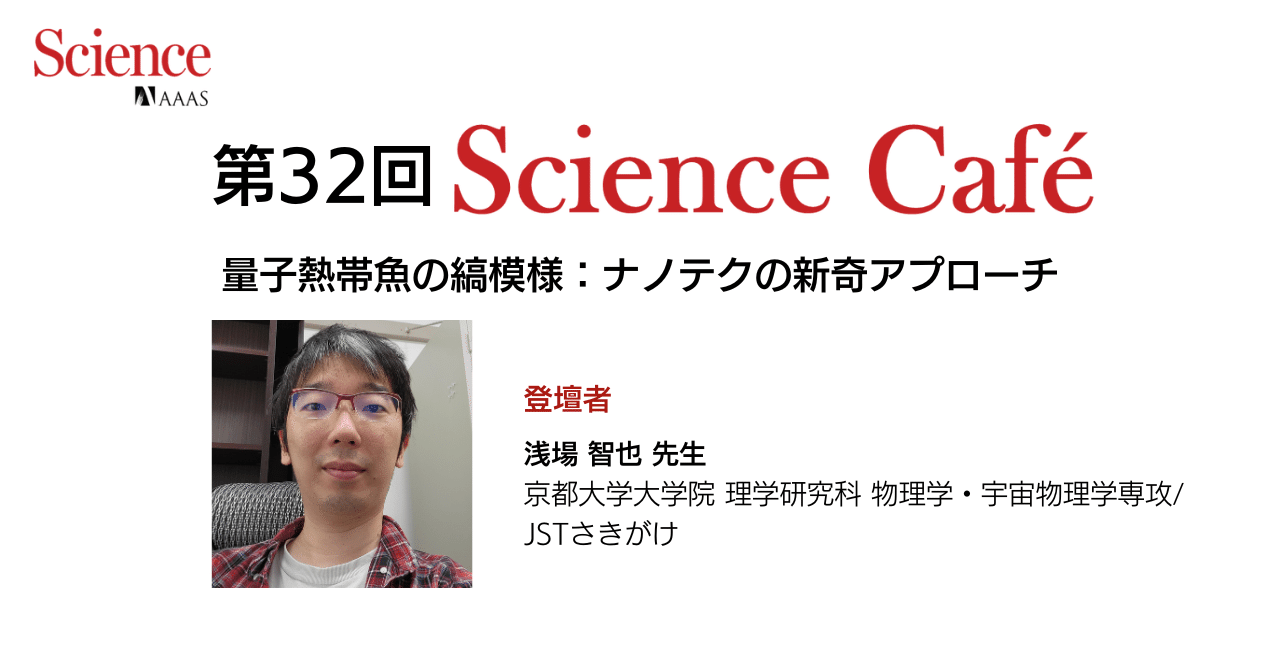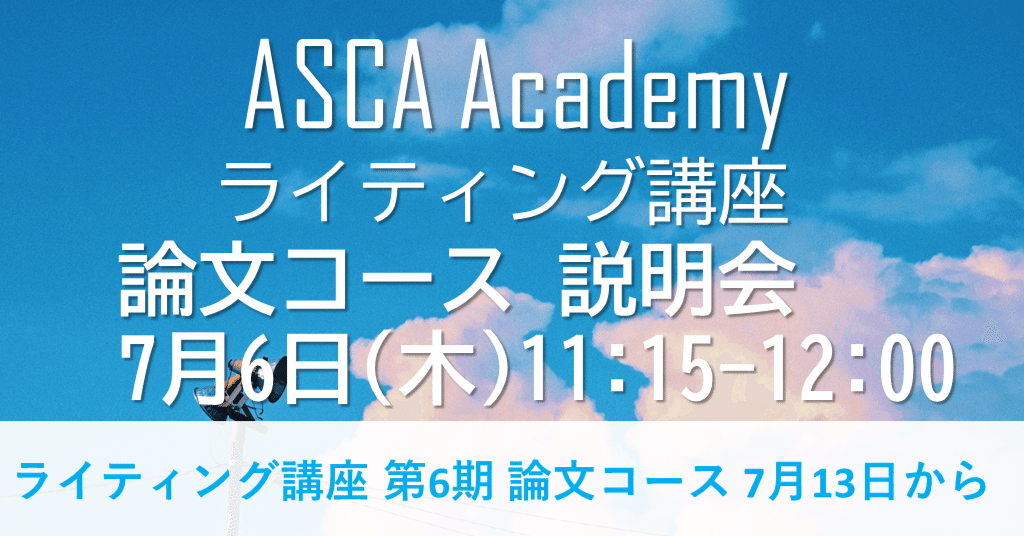
2023年7月より、医薬・サイエンス分野のライティング技術を学ぶASCA Academyライティング講座の第6期がスタートします。今回は「治験文書コース」及び「論文コース」を開催予定です。
論文コースでは、医薬分野のアカデミック・ライティング(論文・学会発表資料作成)の全体像を学ぶことができるよう、①論文・抄録執筆、②図表作成、③スライド・ポスター作成、④QC、⑤研究・出版倫理、⑥論文投稿・学会登録、からなる体系的なカリキュラムをご提供いたします。
講義はすべてオンラインでおこない、世界中どこからでも受講いただけます。講師は、ASCAで日々ライティング業務に携わっている現役メディカルライター(元製薬会社研究開発職)および弊社シニアリンギスト(元学術出版社メディカルライター)が務め、現場の実践的な知識を皆様にお届けします。
少人数制ですので、ぜひ現役ライターの講師と積極的に話し合い、実践的な知識を吸収してください。
講義の録画は、毎回1週間程度、受講生の皆様に共有いたしますので、欠席された場合でも録画受講が可能です。
以下に当てはまる方は、ぜひ参加をご検討ください!
-
メディカルライター志望の方
-
現在は医薬翻訳の仕事をしているが、業務の幅を広げるためにメディカルライティングもできるようになりたい。
-
アカデミック系文書のメディカルライティングに必要な知識を身に着けて、フリーランス等として自立的に働きたい。
-
医薬・バイオ分野の研究者/学生の方
-
研究者/学生として、論文・学会資料の作成で押さえるべきポイントを学びたい。
-
出版倫理についての知識を深めたい。
-
現在は研究者/学生だが、メディカルライターという職業に興味がある。
説明会のお申し込みはこちら※申込み受付を終了しました。
コースの開講に先立ち、見どころなどをまとめた無料セミナーを
7月4日(火)と7月6日(木)に開催いたします。
今回の開催が第6期ラストチャンスです!
ぜひ、ふるってご参加ください。
7月4日(火)11:00~11:45
7月6日(木)11:15~12:00
【説明会の申し込みは下記Formsから受け付けております】
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0iNI7BMbXkWt-LBbtvbjJoNySZe980dHlgl1E8hFaktUQ0xFM1M3TzBYSzlOUjRIRjJEN1EwSlEyQi4u
皆様のご応募をお待ちしております
論文コース詳細
ゴール
論文
① 抄録: 抄録の基本的構造を理解でき、作成できる
② 読解: 英語論文を読解し、要点をおさえた解説資料を作成できる
③ 本文: 臨床に関する英語論文を作成できる
④ 図表: 図表の作成方法を理解し、作成できる
⑤ QC: QCのポイントを理解する
⑥ 倫理: 学術論文の出版倫理について理解する
⑦ 投稿: 投稿時の確認事項、注意点および受理までのプロセスを理解する
学会発表
① 発表資料: 学会発表用ポスター/スライド作成のポイントを理解し、作成できる
② 登録: 演題登録時の確認事項、注意点を理解する
主な学習内容
-
論文の作成目的と基本構成
-
英語論文を作成するために必要なスキル
-
英語論文の各構成パートの実践的な作成方法
-
図表の作成方法
-
発表用ポスター、スライドの作成方法
-
論文QCのポイント
-
おさえておくべき研究・出版倫理
-
英語論文の投稿から受理までの実践的なプロセス
-
学会演題の登録方法
カリキュラム
≪1~3回目≫論文・抄録執筆 (益田講師担当)
① 作成目的
② 各構成パートの概要と作成時の重要ポイント
・タイトル(Title)
・ 著者(Author Information)
・ 要旨または抄録(Summary or Abstract)
・ 緒言(Introduction)
・ 材料及び方法(Materials and Methods)
・ 結果(Results)
・ 考察(Discussion)など
③ 英語論文を作成するために必要なスキル
④ 英語論文の作成に役立つテクニック・知識
≪4~6回目≫図表作成 (益田講師担当)
① 作成目的
② 基本構成
③ 作成時の重要ポイント
④ 作成時に役立つテクニック・ツール
≪7~9回目≫スライド・ポスター作成 (益田講師担当)
① 作成目的
② 基本構成
③ 作成時の重要ポイント
④ 作成時に役立つテクニック・ツール
≪10回目≫QC (倉冨講師担当)
① 論文QC実施時の確認内容
② おさえておきたいポイント、注意点
≪11回目≫研究・出版倫理 (倉冨講師担当)
① 論文出版時に従うべきガイドライン(ICMJE recommendations等)
② 主な注意点:著者要件、利益相反、謝辞、研究倫理に関する情報の開示等
③ メディカルライターの役割
≪12回目≫論文投稿・学会登録 (倉冨講師担当)
① 投稿/登録前に確認すべきこと-規定、登録システム等
② 論文投稿から受理までのプロセス
※回によっては講師より課題が提供される場合もあります。
※カリキュラムは受講生や進捗の状況により、入替えや変更の可能性もございます。
開催方法
・ZOOMを使用してオンラインにて開講いたします。
・益田講師担当分の1~9回(論文・学会資料作成)のみ、倉冨講師担当分の10~12回(出版・研究倫理等)のみの受講も可能です。
募集要項
開講期間
2023年7月開講~2023年12月末終了(予定)
第2・4木曜日14:00~15:30(1時間30分)
※一部不規則な日程となっております。以下のスケジュールをご確認ください。
※ご都合がつかない場合、録画受講も可能です。

受講条件
・オンライン講義に対応できるPC環境を整えられる方(カメラ、マイクセットなど含む)
・講師やほかの受講生と積極的に意見交換ができる方
受講料
全12回受講の場合、益田講師担当分の1~9回のみの場合、倉冨講師担当分の10~12回のみの場合で、それぞれ受講料が異なります。
1.全12回 税込66,000円
2.1~9回(論文・学会資料作成) 税込52,000円
3.10~12回(出版・研究倫理等) 税込18,000円
※お支払いは銀行振込み、クレジットカード支払い、コンビニ支払いをお選びいただけます。
※特別割引適用あり
以下の①~③のいずれかに当てはまる方は、10%割引にてご受講いただけます
① アスカコーポレーションの登録翻訳者、ライター、チェッカー
② 第1期~第5期までの修了生
③ 大学生、大学院生
定員
定員:10名程度
※最低開講人数:8名。8名に達しない場合、開講を見送る場合がございます。
応募について※申込み受付を終了しました。
・応募締め切り予定:7月6日(木)17時
※応募状況によっては、締め切りが変動する場合がございます。
参加ご希望の方は下記フォームよりお申し込みください
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0iNI7BMbXkWt-LBbtvbjJoNySZe980dHlgl1E8hFaktUQVpTWlQ4SVpRV0I2RjQzNDRFOFEzRlFGMy4u
担当講師
益田 和義
フリーランスメディカルライター。薬学博士(大阪大学)、工学修士(早稲田大学)。
内資系製薬会社の研究所に22年間勤務し、17年間はDrug Delivery Systemの研究に,その後5年間は探索ADME (Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion) に関する開発研究に従事した。この間に16報の論文発表及び6件の特許出願を行い,開発研究では10以上の開発化合物を選出している。その後開発部に異動し,非臨床担当責任者として13年間で10以上の開発プロジェクトを承認申請に向けてリードした。退職後は、フリーランスのメディカルライターとして、市販後資材、学会発表資料、論文、IB並びにCTDなどの医薬品に関する資料の作成支援を行っている。
https://note.asca-co.com/n/nc99d49dd0071
倉冨剛
アスカコーポレーション ソリューション事業部3 部長・シニアメディカルライター。医学博士(東京大学)、理学修士(東京工業大学)、ISMPP Certified Medical Publication Professional™ (CMPP™)。
精神医学分野でPh.D.を取得後、外資総合系コンサルティングファーム、医学部教員、外資学術出版社メディカルライター、フリーランスを経て現職。専門は生物学的精神医学、脳神経医学、分子遺伝学、細胞生物学。メディカルライターとして、原著論文・総説執筆(臨床試験、市販後調査等)、学会発表資料作成、文献調査等に携わる。現職では、ライティング・QCプロセスのマネジメント等を主な職務とするが、個別案件のライティングやQCにも関わる。
https://note.asca-co.com/n/nee203a3614e6
お問い合わせ
下記リンク先のお問い合わせフォームよりお問い合わせください
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0iNI7BMbXkWt-LBbtvbjJoNySZe980dHlgl1E8hFaktUOEYzWklPUkNRS0FNQTBNTERaWjBCRlI4RS4u