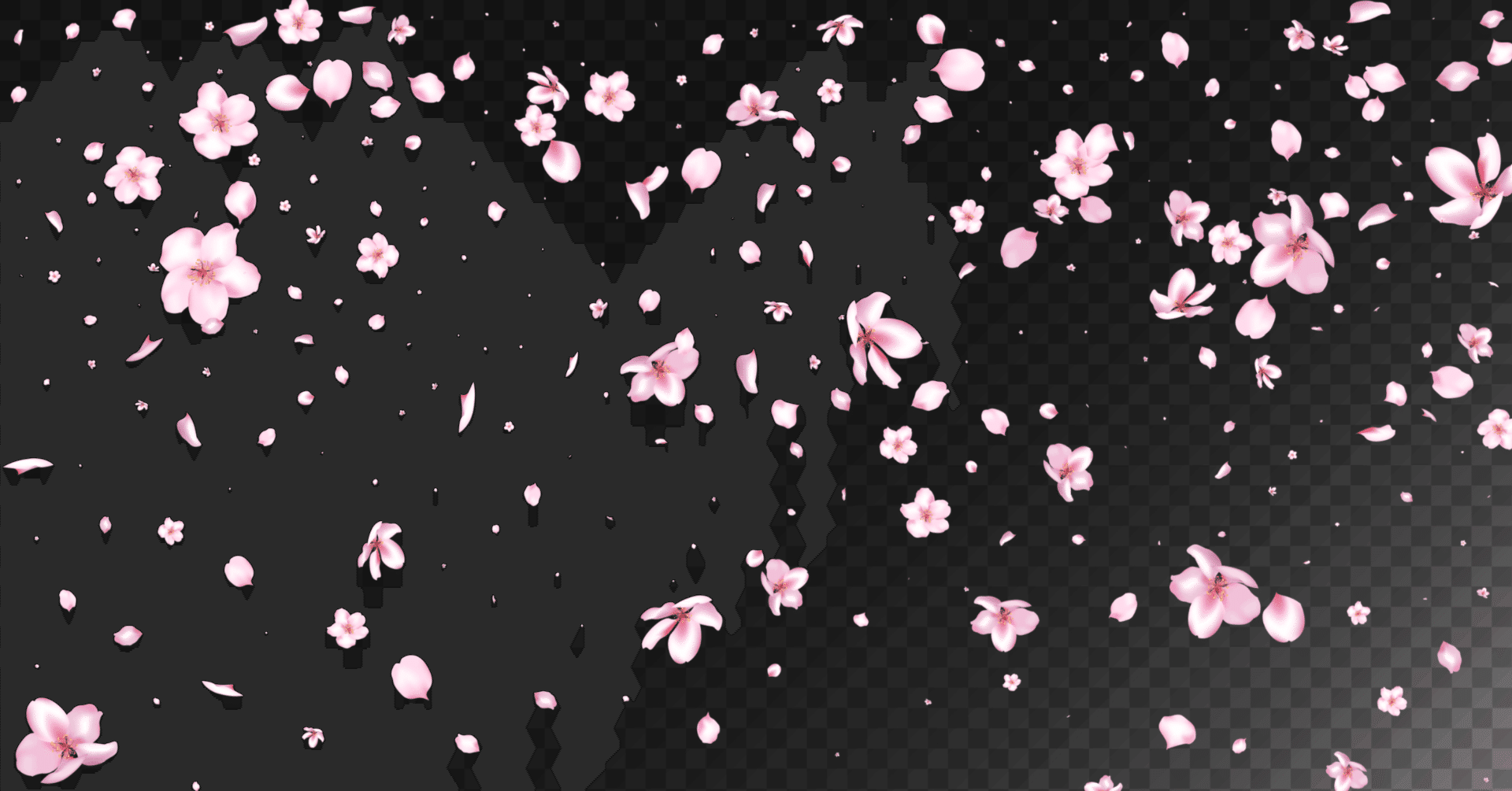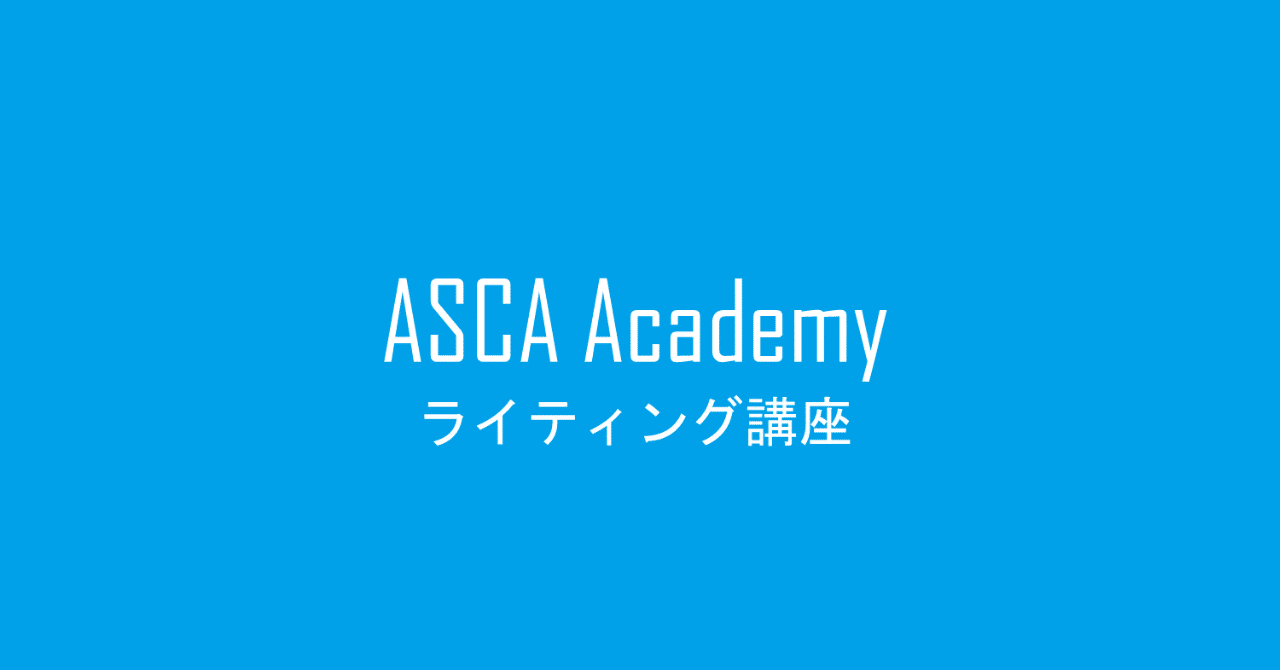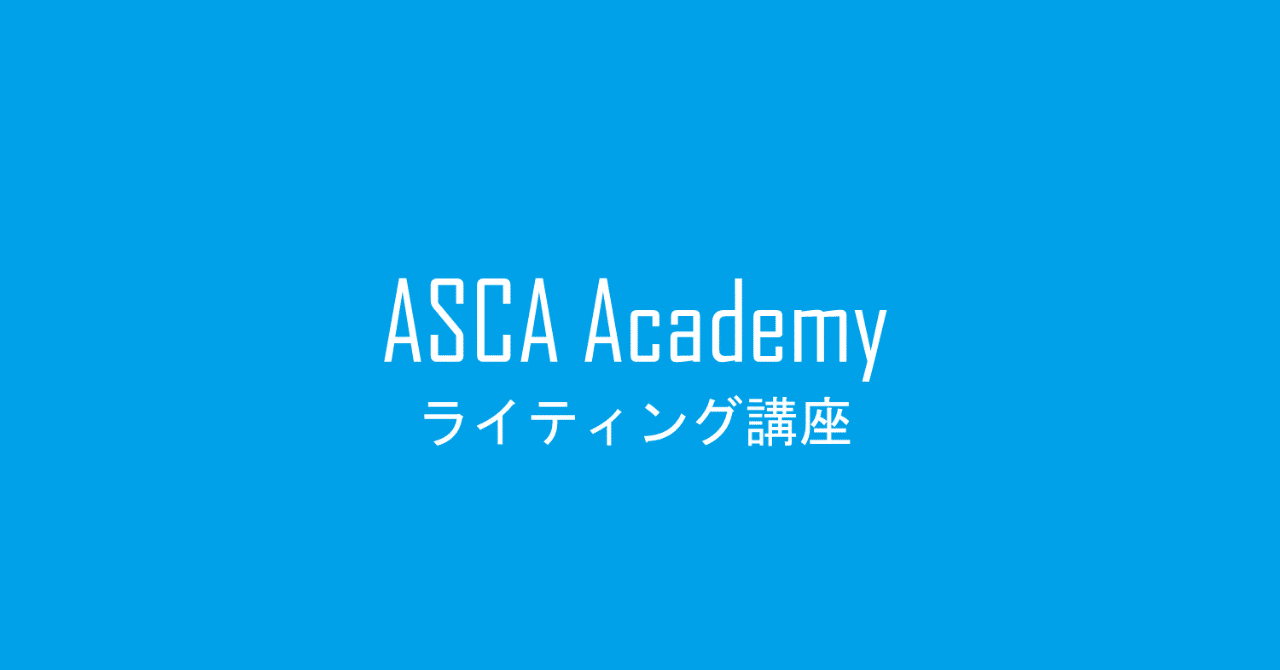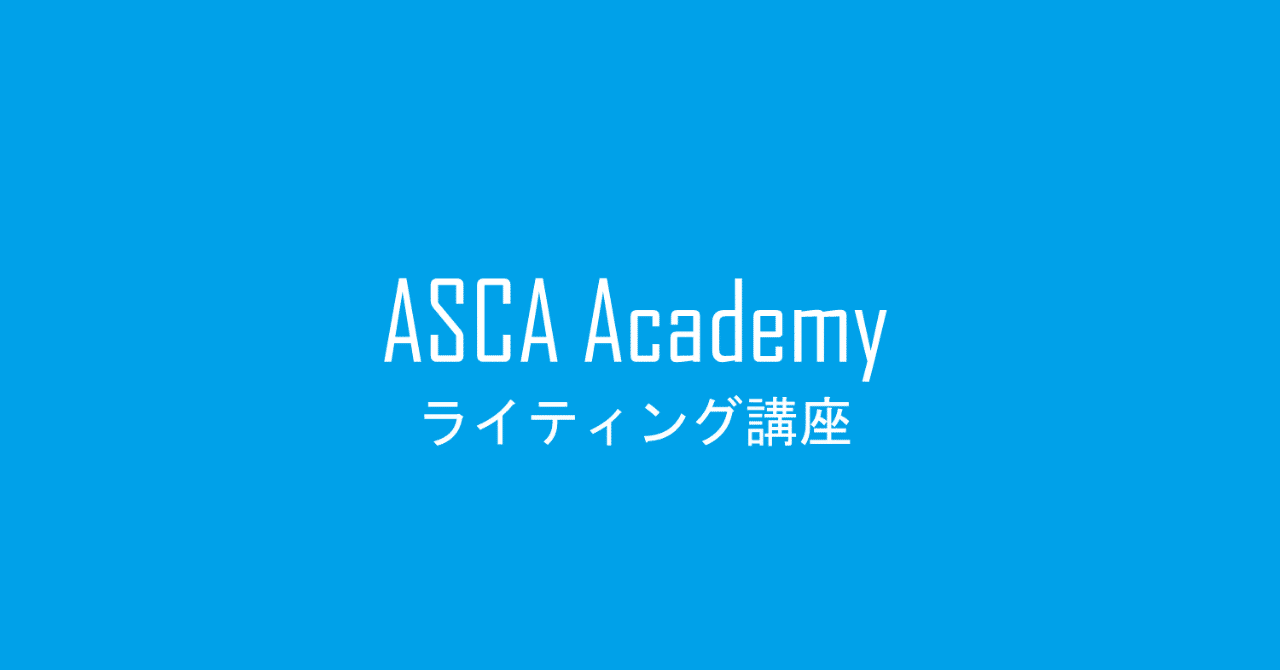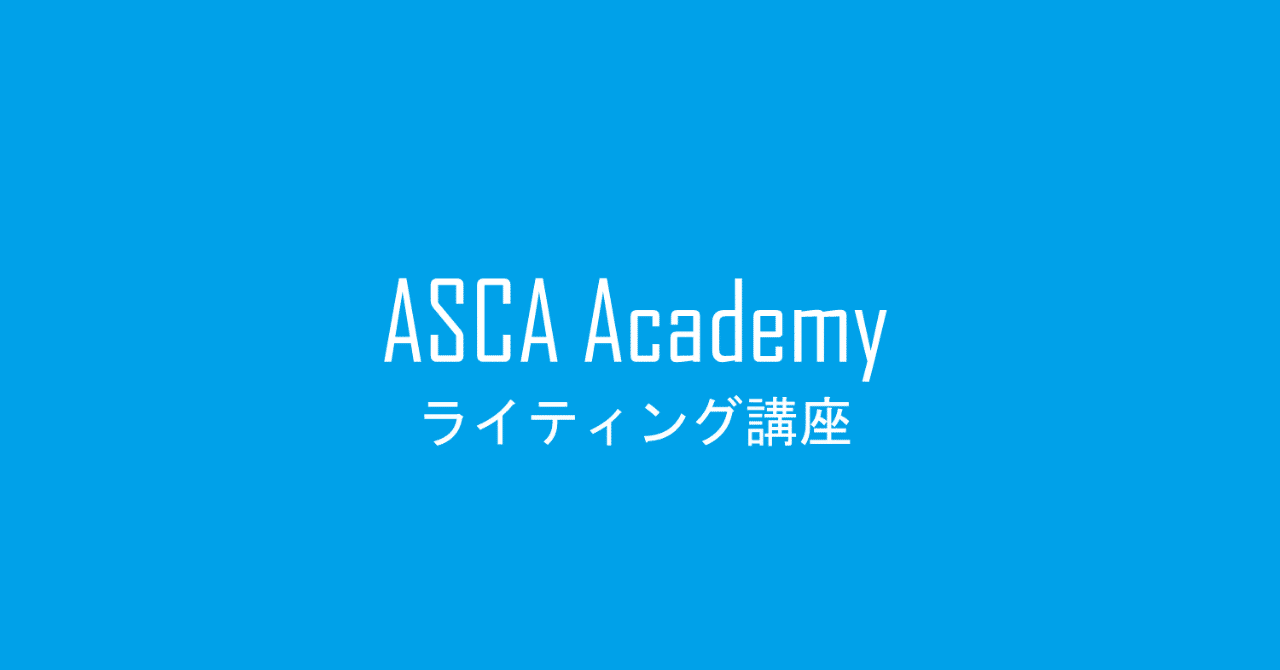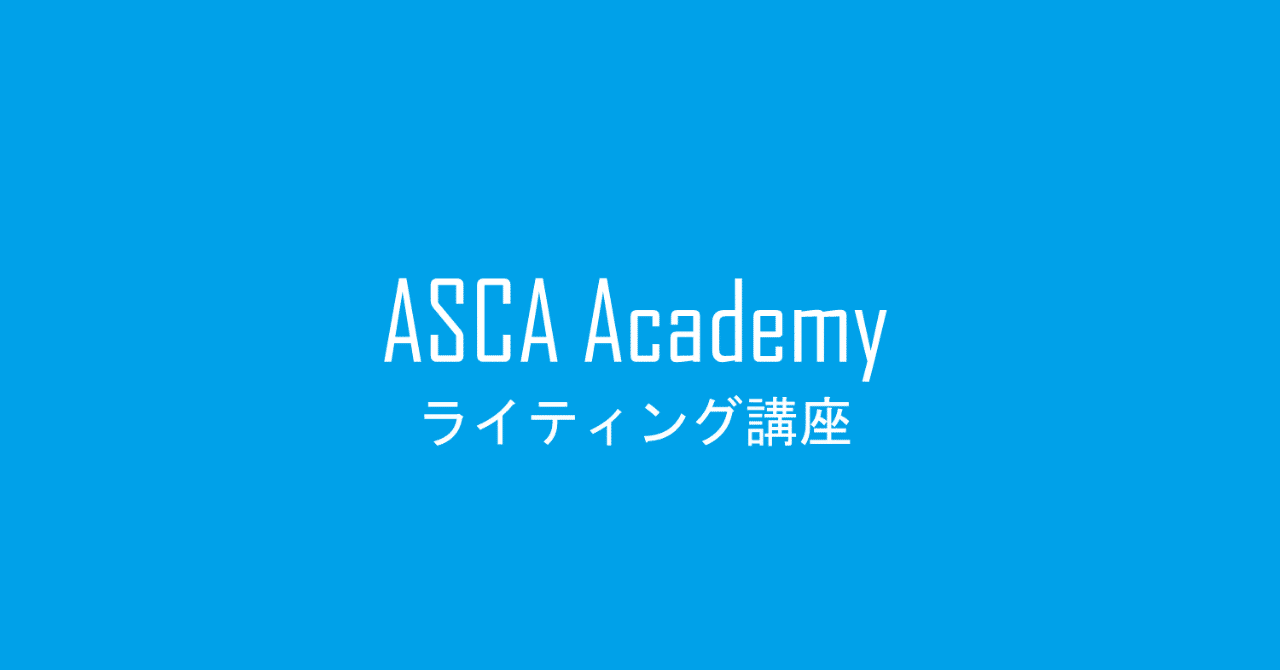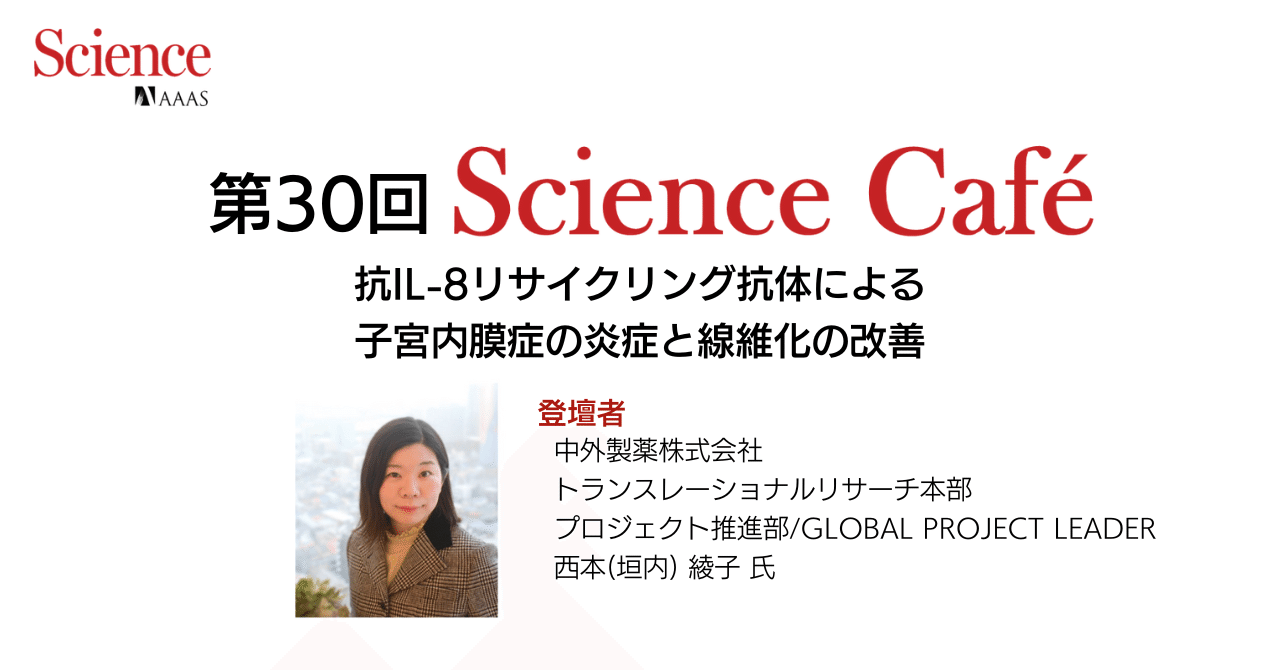
Science Cafeのご案内
Science Café はScienceまたは姉妹誌に研究論文等投稿が掲載された日本研究者の方にZoom Webinarによるライブ配信にて講演して頂くイベントです。
研究内容の解説に加え、研究にまつわるエピソード、社会に与える影響や提言を交えてお話して頂きます。Q&Aセッションも設けております。参加は無料です。
日 時:2023年5月30日(火)14:00~14:40(予定)
タイトル:抗IL-8リサイクリング抗体による子宮内膜症の炎症と
線維化の改善
演 者:西本(垣内) 綾子 氏
中外製薬株式会社トランスレーショナルリサーチ本部
プロジェクト推進部/Global Project Leader
概要
子宮内膜症は、20-40歳代の女性の10人に1人が罹患しており身近な婦人科疾患です。強い月経痛だけでなく、慢性的な下腹部痛や不妊症の原因にもなるため、患者さんの生活や人生を変えてしまうこともある疾患です。標準治療薬はホルモン剤で月経を止めて症状を緩和しますが、わたしたちは月経や排卵を止めない非ホルモンの薬剤を目指し、子宮内膜症の炎症や線維化とIL-8の関係に注目しました。本研究では従来型抗体の限界や動物モデルの限界を乗り越えて、誘引サルモデルを用いて抗IL-8リサイクリング抗体による子宮内膜症の炎症と線維化改善を示しました。産官学の共同研究によりどうやって研究の壁を乗り越えたか、についてもご紹介いたします。
掲載号:Science Translational Medicine 2023年2月22日号
“A long-acting anti–IL-8 antibody improves inflammation and fibrosis in endometriosis”
SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 22 Feb 2023 Vol 15, Issue 6841 DOI: 10.1126/scitranslmed.abq5858
中外製薬株式会社HP:
https://www.chugai-pharm.co.jp/
西本氏 LinkedIn:
https://jp.linkedin.com/in/ayako-nishimoto-kakiuchi-amy109
お申込み
以下のURLよりお申込みください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2HXZ5Kv7Rzuci_9GMGoRcw
ご登録いただく際、名、姓の順での記載となっておりますのでご注意下さい。また、確認メールにおいて敬称が省略される場合がありますことを予めご了承ください。
*定員になり次第、締め切りよりも前に締め切る場合がございますので、予めご了承ください。
お問合せ先
Science Japan Office 担当:ランベッリ律恵
E-mail: science_cafe_japan@asca-co.com
講演を終えて
第30回Science Café「抗IL-8リサイクリング抗体による子宮内膜症の炎症と線維化の改善」、が5月30日に開催された。Caféでは企業研究者初、中外製薬株式会社トランスレーショナルリサーチ本部プロジェクト推進部/Global Project Leader西本(垣内) 綾子氏の発表である。
子宮内膜症は、20~40歳代女性の10人に1人が罹患している身近な婦人科疾患である。強い月経痛、慢性的な下腹部痛や不妊症の原因にもなり、患者の生活や人生を変えてしまうというのに、ホルモン剤を使う治療に頼らざるを得ないのが現状で、未だ根本的な治療法が開発されていない。今回の研究では、月経や排卵を止めない非ホルモンの薬剤開発としてIL-8に注目した。炎症性サイトカインであるIL-8が子宮内膜症の炎症と線維化の進展に関与し、IL-8を制御することが病態改善につながることが確認できたのである。子宮内膜症に対する新たな治療薬につながるに違いない。
そもそも子宮内膜症の研究は難しい。ラットやマウスには月経がない(内膜がはがれない)ため、実験には使えない。そこで、NIBIOHN 霊長類医科学研究センターの協力を得て、子宮内膜症自然発生モデルのカニクイザルを実験に使うことで今回の研究が可能になったのだという。その上、子宮内膜症自然発生カニクイザルは稀有で、均質化も難しい。それゆえ、自治医科大学付属埼玉医療センターの助けを借り、ビデオモニターによる所見観察、病変採取を実現することで、病態メカニズムの解明につなげた。まさに、産官学のエキスパートによる努力の集積と15年にもおよぶ長期共同研究が今回の成果である。
そうした外部の力と、社内の研究者のパッション、お互いの研究をリスペクトすることが秘訣だと語る西本氏。今回の研究が国内外で注目されることで、女性の健康を損なう子宮内膜症の注目度を高め、患者さんや周りの人たちが、より活き活きと生活できる社会の実現に貢献したいとおっしゃっていた。
医者は目の前の患者さんしか助けられないが、薬学研究者は世界中の患者さんを救うことができるすばらしい仕事である、と医師に助言されたことが励みになっているという。名言である。
さまざまな専門性を活かす一方で、自分とは違った研究に触れることが重要であるとも語っておられた。くじけそうになったこと、逃げたくなったことも何度もあったに違いない。それでも笑顔で研究のすばらしさを伝える西本氏の姿に、私たちは勇気をもらった。ますますの研究の成果を心から応援したい。
文:Science Japan Office
掲載号:Science Translational Medicine 2023年2月22日号
“A long-acting anti–IL-8 antibody improves inflammation and fibrosis in endometriosis”
SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE 22 Feb 2023 Vol 15, Issue 684 DOI: 10.1126/scitranslmed.abq5858 子宮内膜症の研究
中外製薬ニュースリリース:
抗IL-8リサイクリング抗体AMY109、子宮内膜症の炎症と線維化改善に関する産官学での非臨床試験の成果がScience Translational Medicineに掲載
https://www.chugai-pharm.co.jp/news/detail/20230224113000_1286.html?year=2023&category=