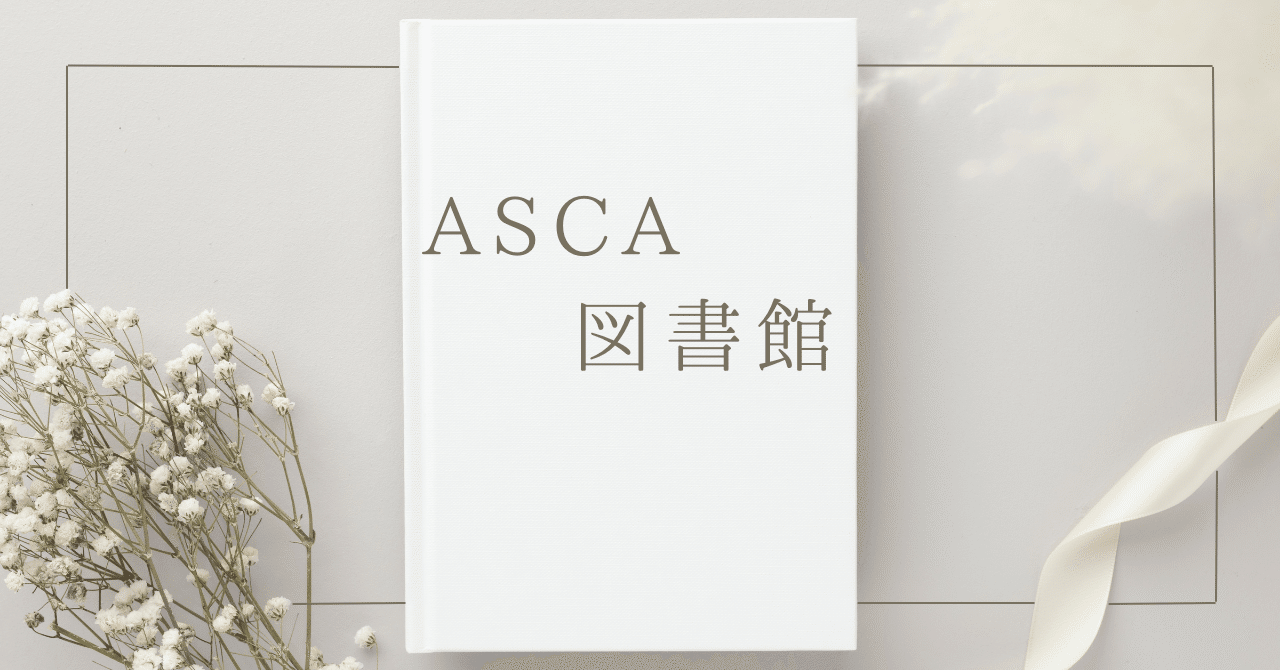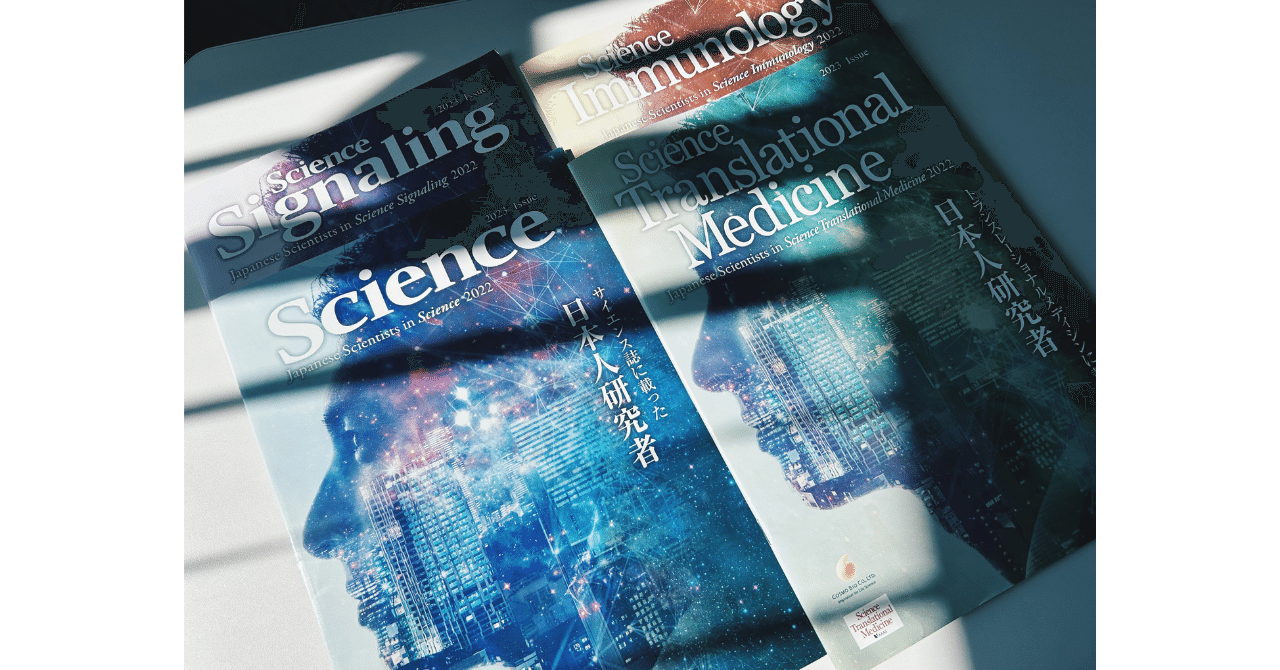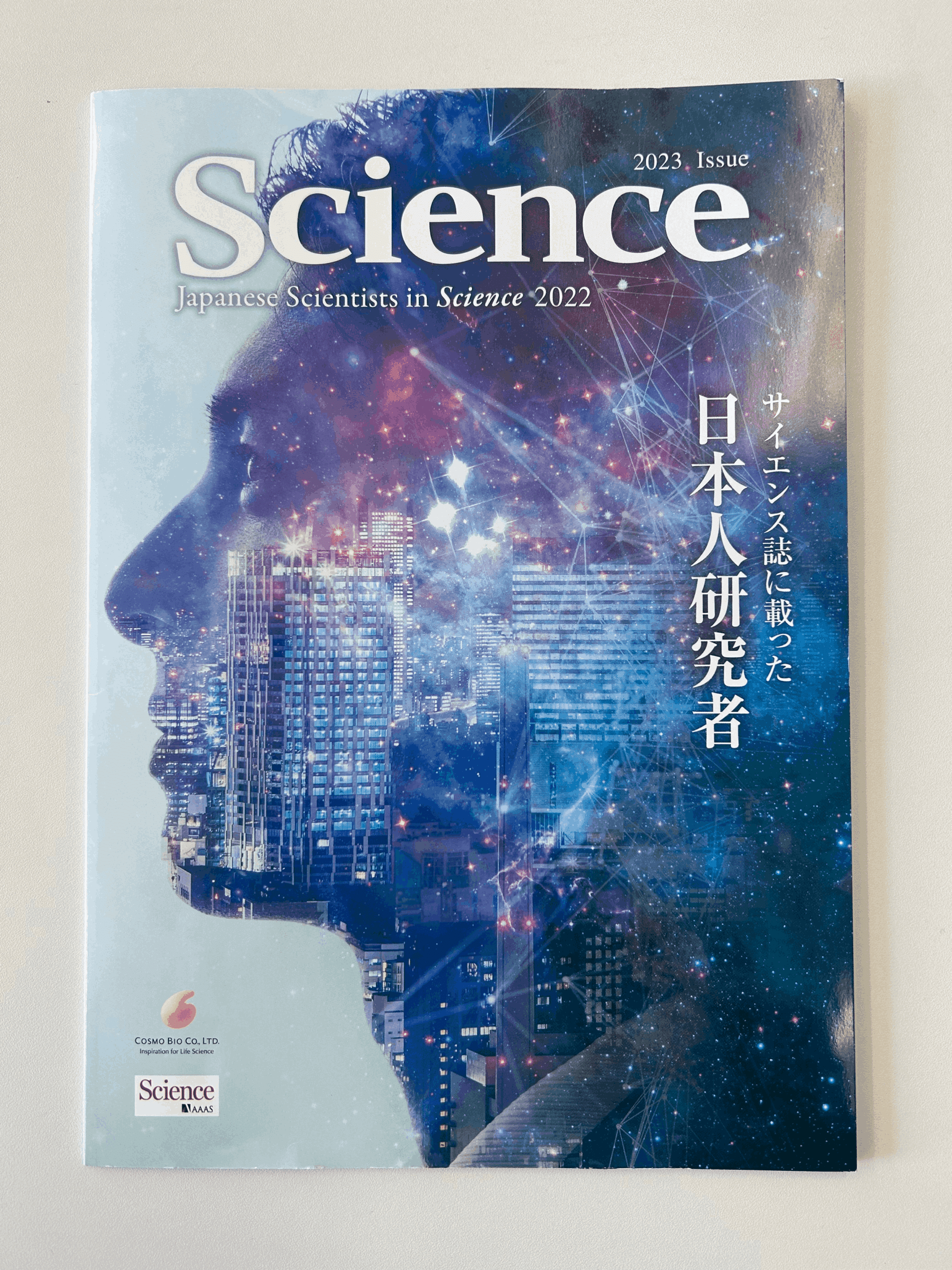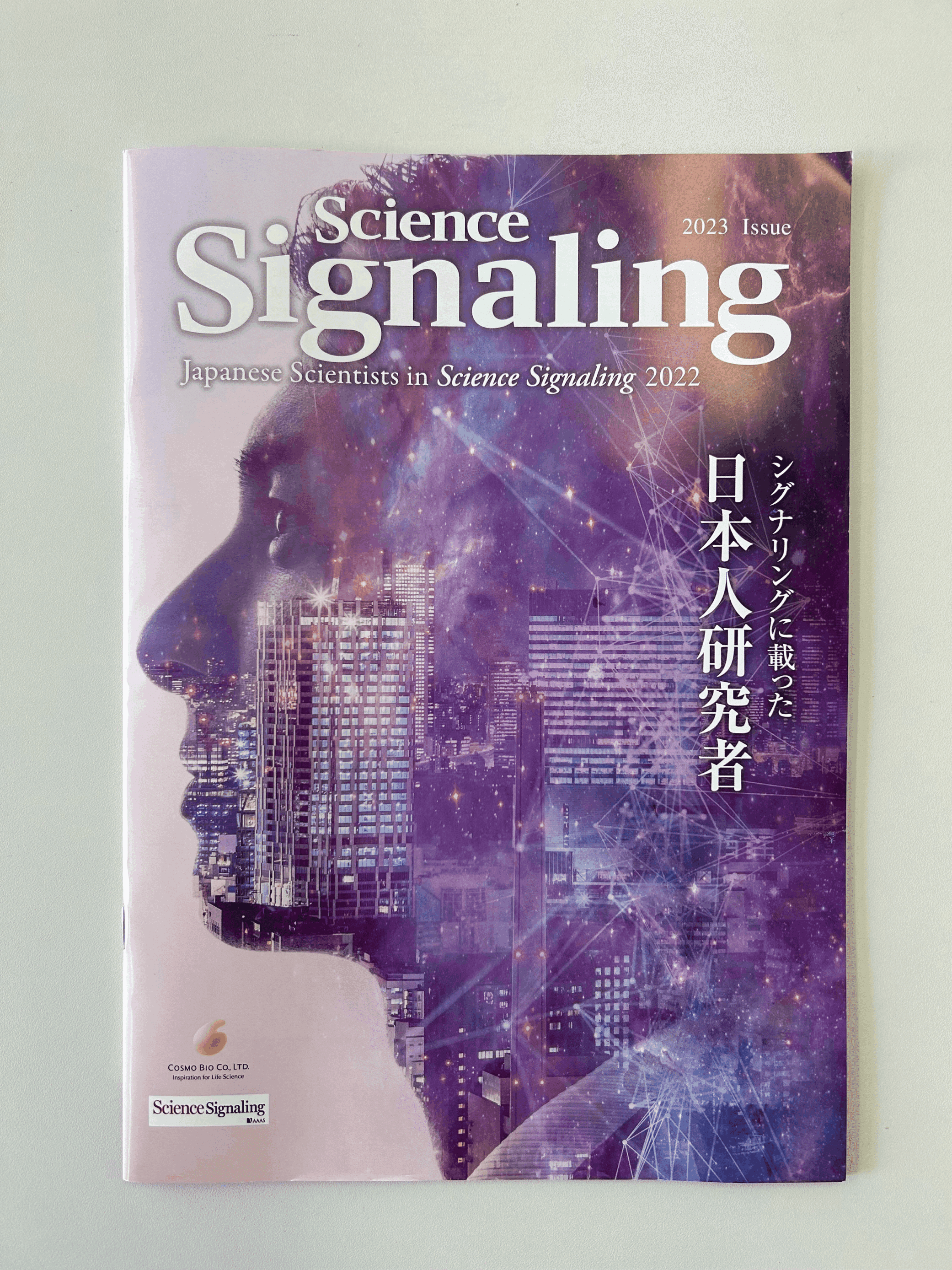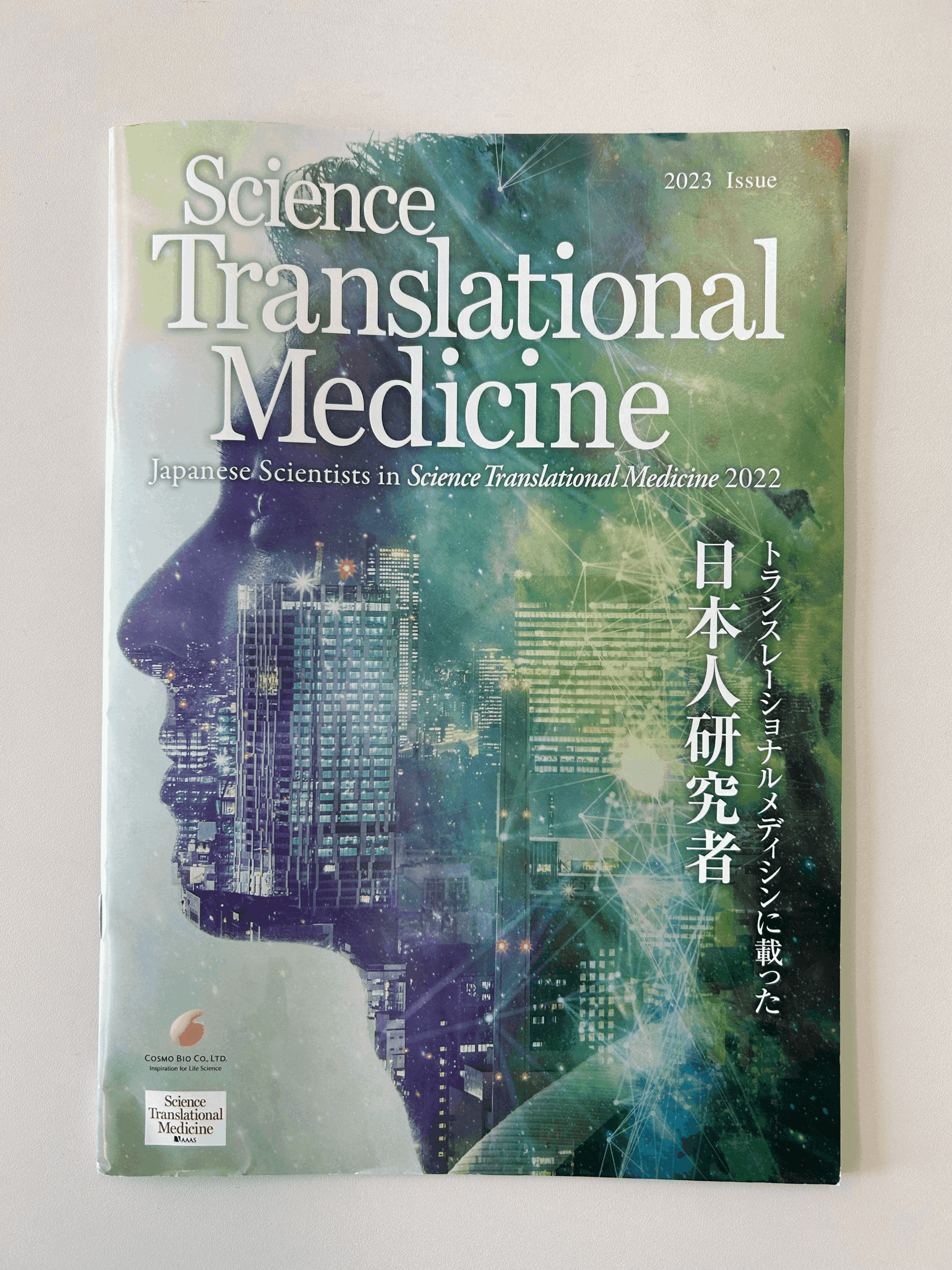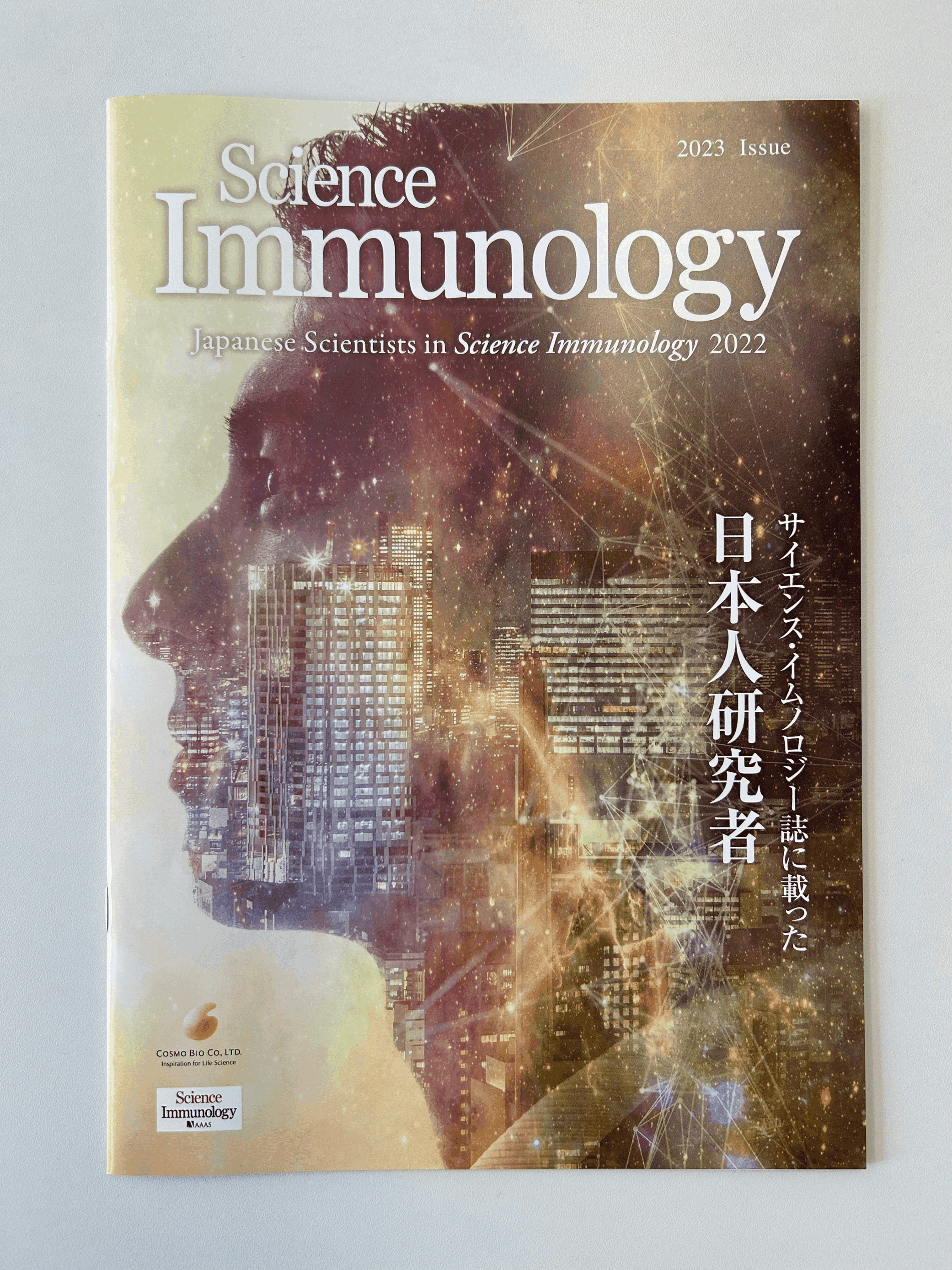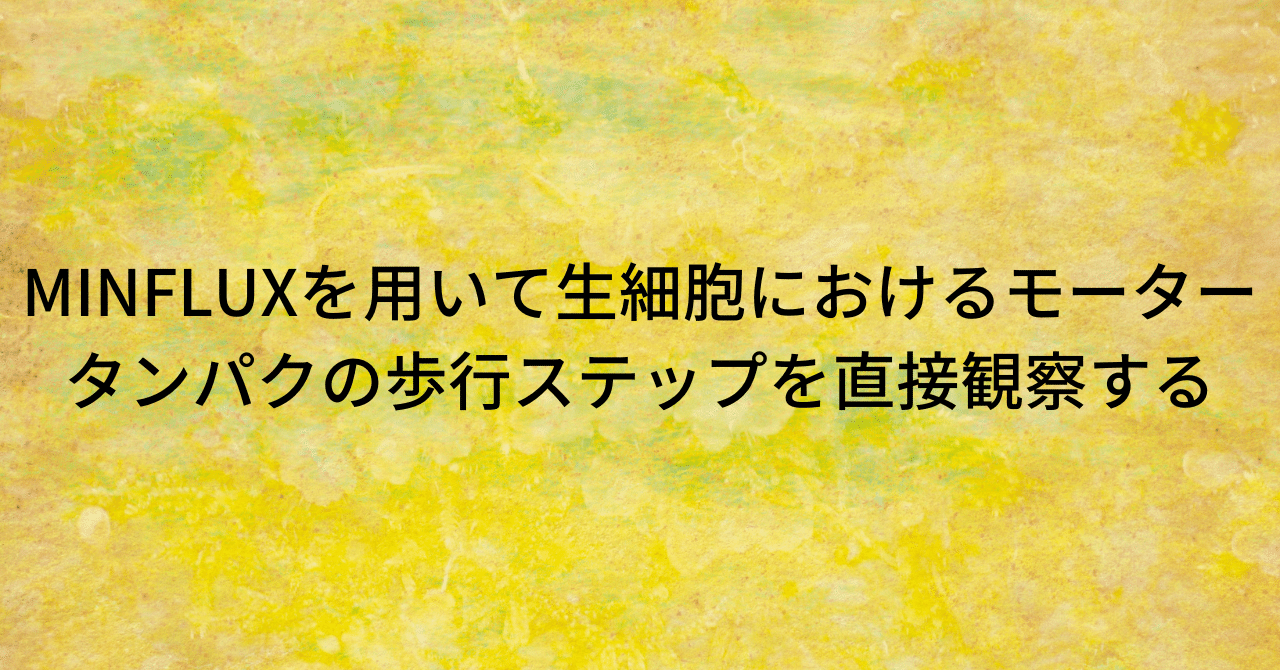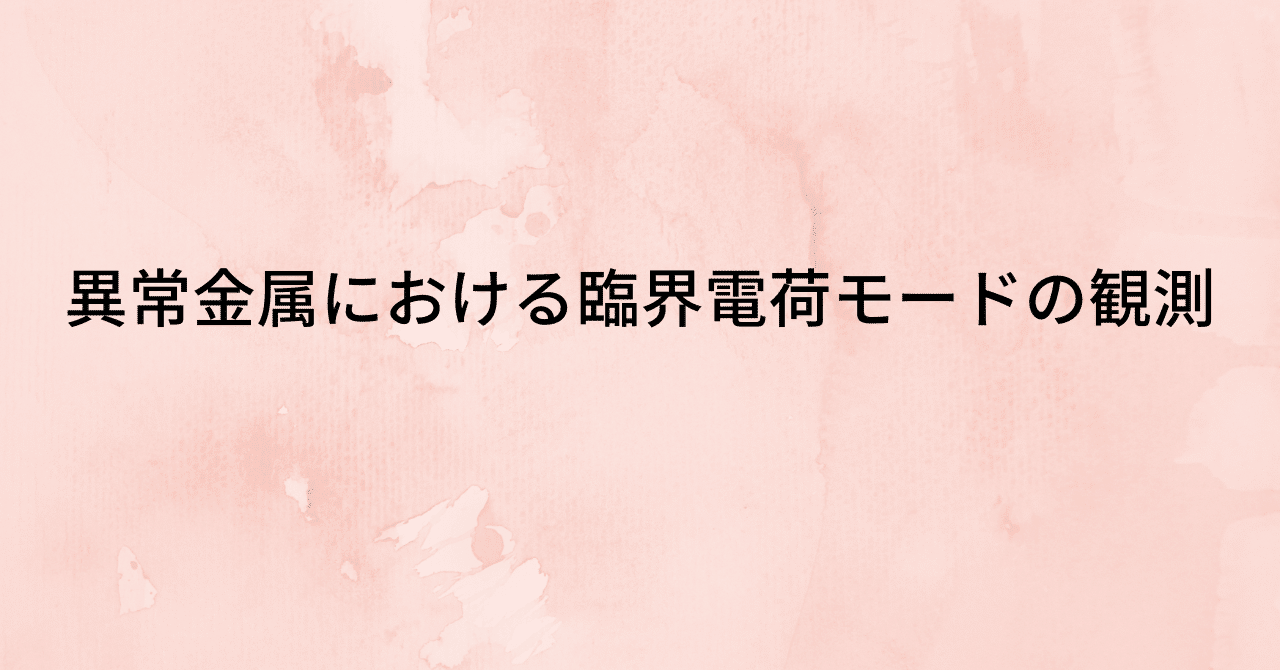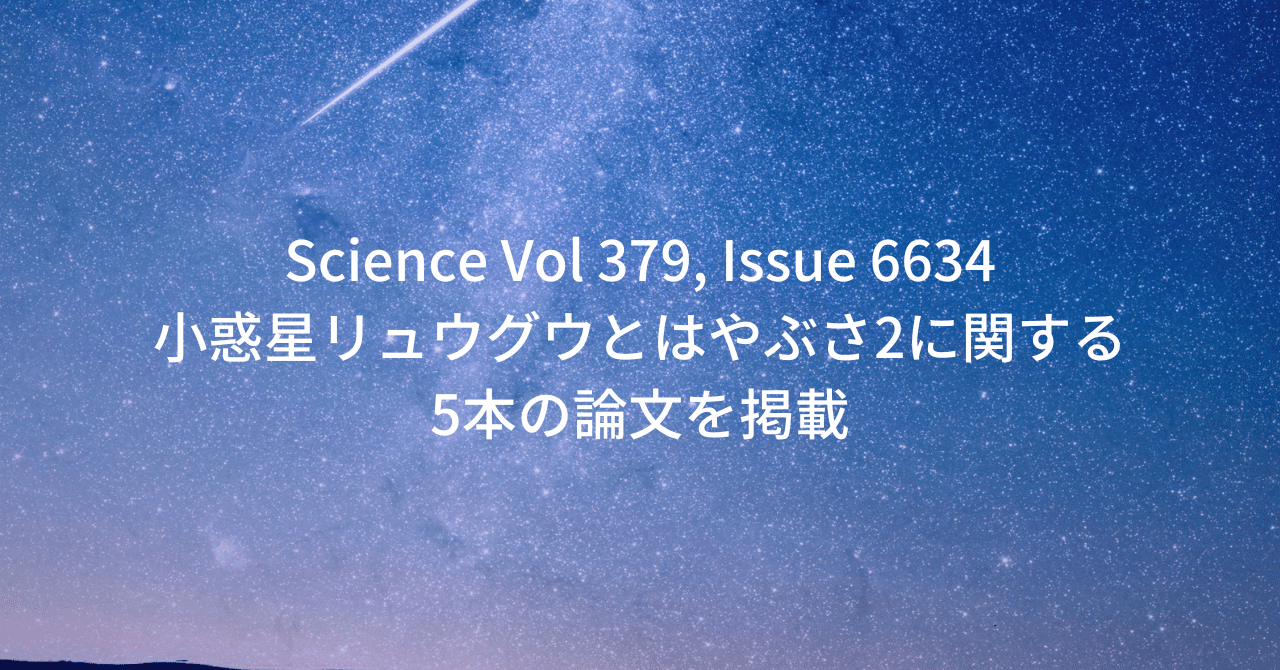※本コースは終了いたしました
将来的にCTDなどのライティング業務に携わるために、以下の内容が理解できるような場を提供します。
ASCA Academy ライティング講座 第2期の概要についてはこちら
ゴール
-
CTDの臨床パートの内容が理解できる
-
英語のCTDから日本語のDraft CTDを作成するときの記載内容や参照資料が理解できる
主な学習内容
-
医薬品開発全体
-
医薬品の臨床開発戦略
-
CTDの臨床パートで求められる情報
-
関連するガイドライン
-
CTDの記載内容
カリキュラム
1回目(無料公開講座)
医薬品開発の概観~臨床開発段階を中心とした概観~
2回目(無料公開講座)
コモンテクニカルドキュメント(CTD)とは?~臨床モジュール(Module 2.7)の記載内容の概観~
3回目
Module 2.7.1:生物薬剤学試験及び関連する分析法①~製剤開発プログラムと製剤間ブリッジング~
4回目
Module 2.7.1:生物薬剤学試験及び関連する分析法②~記載すべき内容と参照すべきガイドライン~
5回目
Module 2.7.2:臨床薬理試験①~薬物動態(PK)及び薬力学(PD)~
6回目
Module 2.7.2:臨床薬理試験②~PKに影響を及ぼす可能性のある要因:相互作用、特別な集団~
7回目
Module 2.7.2:臨床薬理試験③~その他、臨床薬理パートで評価する内容:心電図(QTc延長)、免疫原性~
8回目
Module 2.7.2:臨床薬理試験④~記載すべき内容と参照すべきガイドライン~
9回目
Module 2.7.3:臨床的有効性①~対象集団、主要評価指標と副次的評価指標など~
10回目
Module 2.7.3:臨床的有効性②~記載すべき内容~
11回目
Module 2.7.3:臨床的安全性①~安全性評価指標:有害事象など~
12回目
Module 2.7.4:臨床的安全性②~記載すべき内容~
*毎回の講義では講師より課題が提供されます。
*カリキュラムは受講生や進捗の状況により、入替えや変更の可能性もございます。
担当講師
三宅 義昭
エムプラスオー代表。株式会社アスカコーポレーション 顧問
外資系製薬会社に21年間勤務し、この間に複数のプロジェクトの臨床開発、臨床薬理試験を含む早期臨床開発計画、アウトソース戦略立案などの業務経験を経て独立。フリーランスとして、医薬品の開発業務の支援を行っている。近年は、協働する企業や個人ライターなどと協働し、リソースを最適化して、CTDや市販後資材などの医薬品に関する資料作成支援を行っている。
応募フォーム
2020年9月8日をもって、申込み受付を終了しました
お問い合わせ先
ASCA Academyライティング講座事務局
株式会社アスカコーポレーション
担当:伊藤・西澤
電話:06-6202-6272
メール:writing_school@asca-co.com
※本コースは終了いたしました