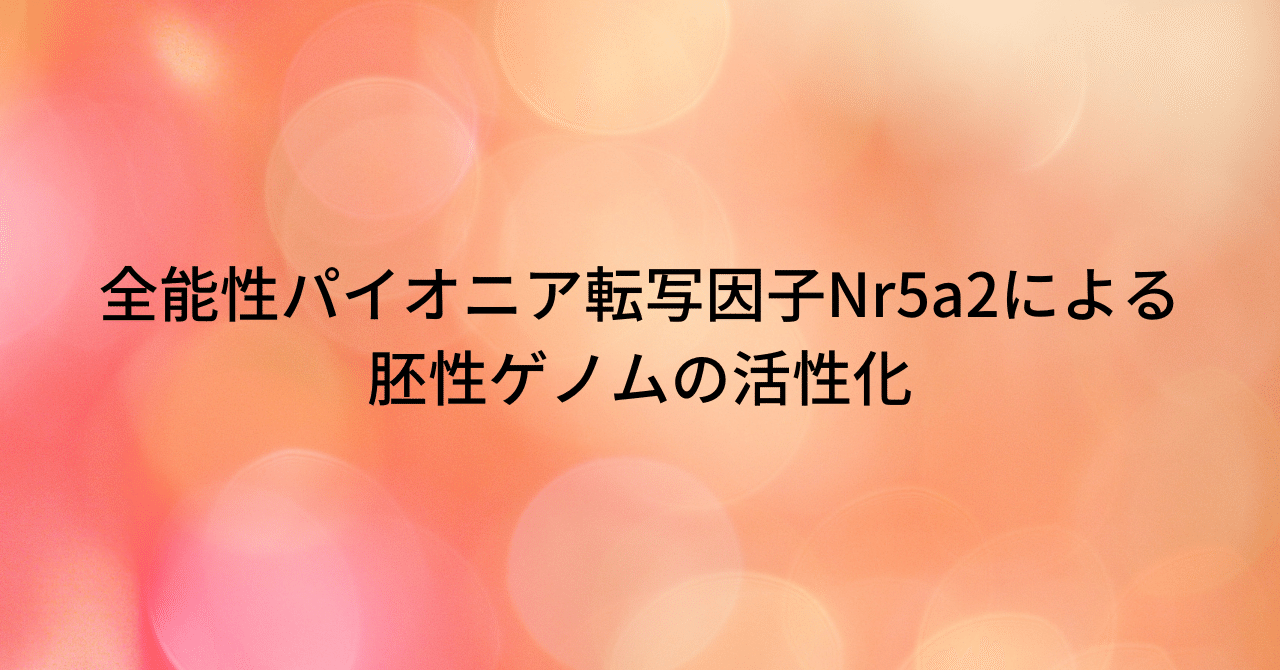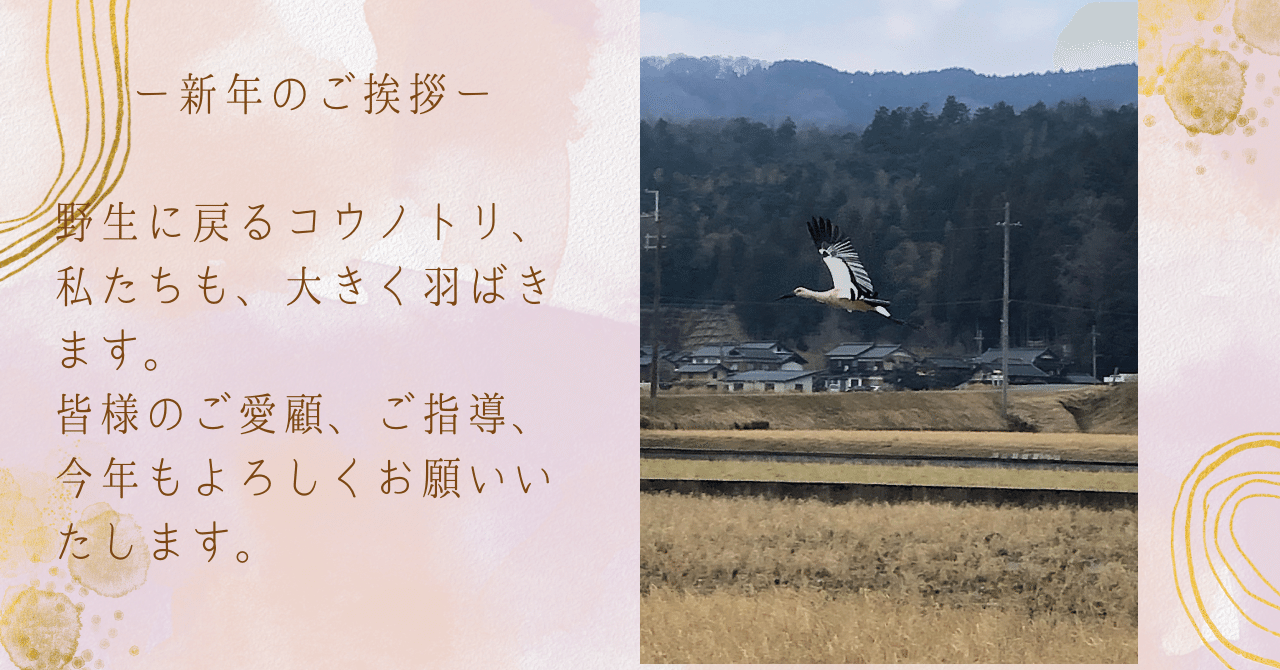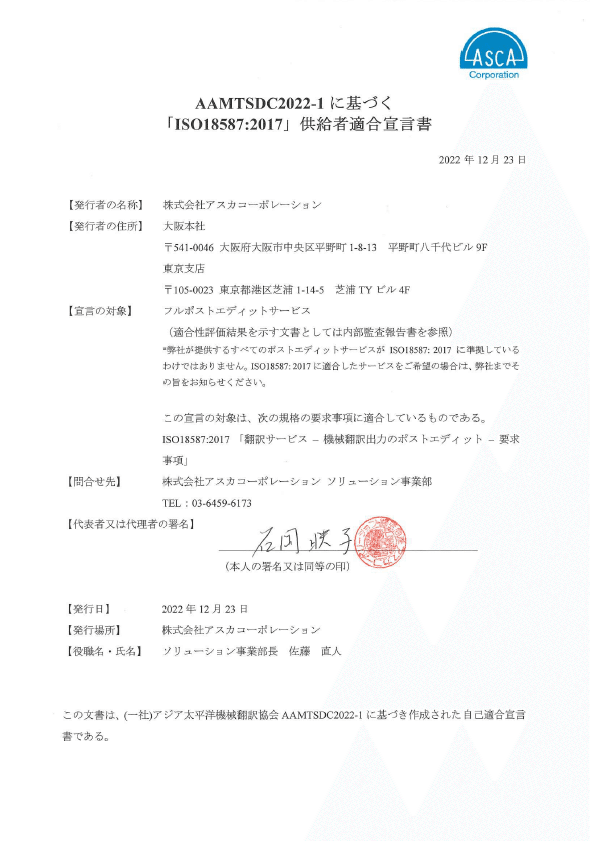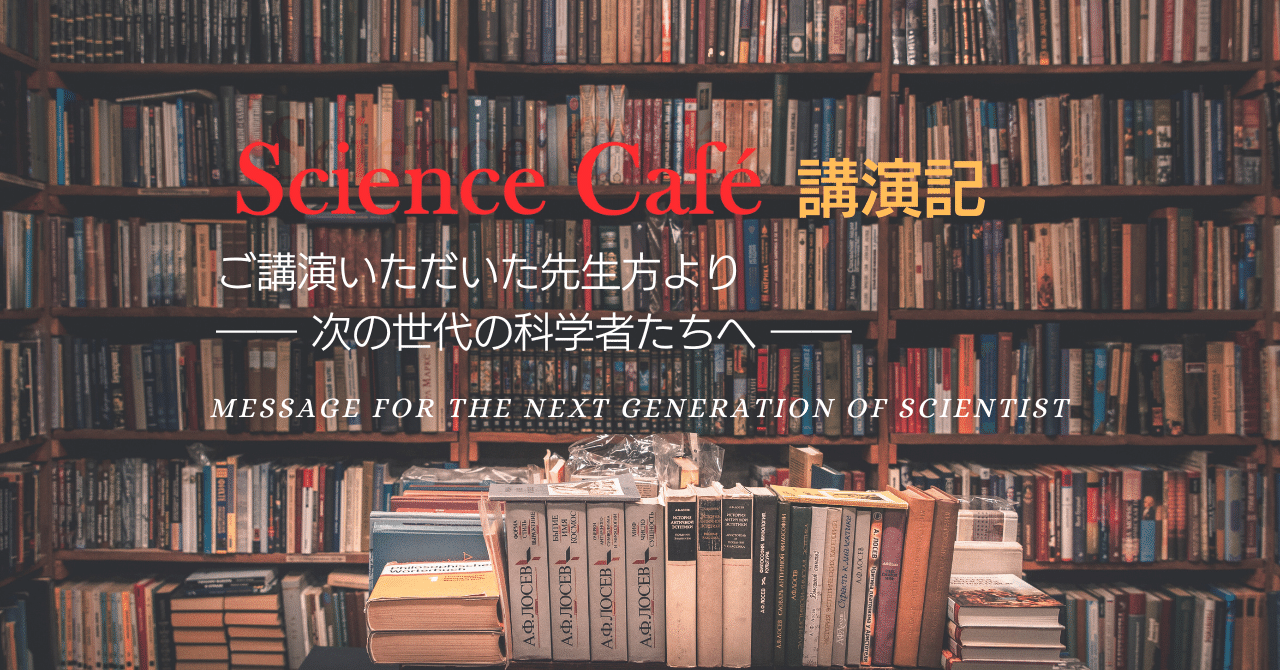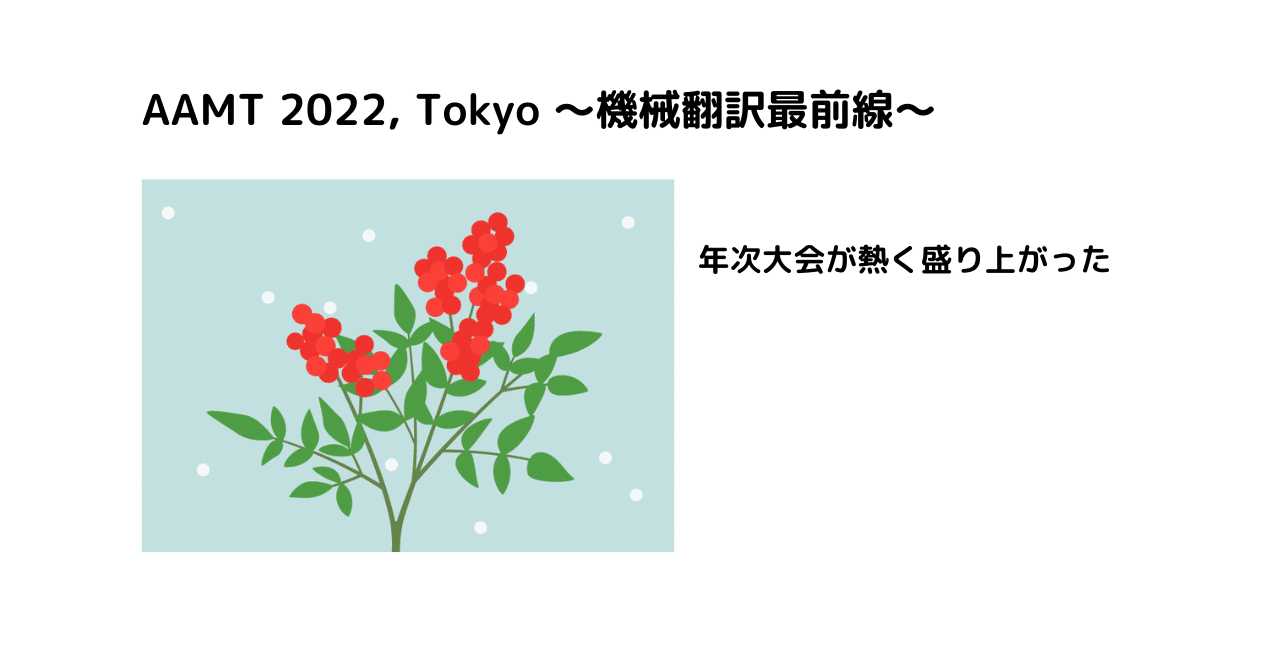論文にメッセージを込める。査読者や読み手にとって何を伝えたいかというメッセージを明確にすることで、テーマがぶれない明確な論文になる。それは研究のテーマとも共通し、自分を支える軸になる。
第48回講演者
https://note.asca-co.com/n/n260cf05c1287
神経科学の技術革新が今まさに起こっている。今回の研究では、シナプスを操作する分子ツールを用いてシナプス増強による睡眠の誘導を観察し、そのメカニズムを計算的な手法で解析できた。このことは睡眠研究の歴史に新たな局面を開くことになるだろう。
第46回講演者
https://note.asca-co.com/n/n12759e6e3d0e
研究は失敗の連続で、苦労の日々ばかりだと思います。
研究は、時々素晴らしいものを見せてくれます。この研究でも、生命の造形の美しさに出会うことができました。それは、私がこの仕事を続ける理由の一つです。また、研究を通じて、日本の様々な場所や海外で働いたり、宇宙実験に携わるなど、自分では想像もつかなかった経験をさせてもらい、その過程における人との出会いは得難いものでした。
研究は、楽しんだり苦労したりしながら、時に素晴らしいことや美しいものにめぐり逢う人生と通じるものがあるように思います。
ただし、「研究」の部分を他の言葉に変えたくなったらそれも良いと思います。研究以外にも素晴らしいことは数多く存在し、研究を通じて培われた考え方や問題解決法は、人生を豊かにしてくれると信じています。
第45回講演者
https://note.asca-co.com/n/n2d91a983676f
論文は “Simple and impressive” で書く。理解しやすい筋道と概念のおもしろさを組み入れられるように、最初にコンセプトを考える時間を大切にしています。
第44回講演者
https://note.asca-co.com/n/nfb0858585de0
サイエンスって楽しい!面白い!
第43回講演者
https://note.asca-co.com/n/na5ef583d51c2
大勢の人が同じものを見ていても、人によって気付くことは違っている。研究結果を目前に、その重要性に気付くかどうかは、結果と丁寧に向き合い、より深く観察する姿勢から得られるものである。
第42回講演者
https://note.asca-co.com/n/n9e2bd687df93
良くも悪くも自分の成果をが純粋に評価される研究の世界。明確な目標が見つけられない時も、自分ができることをとにかく一生懸命やろうと心に決めて続けてください。
第41回講演者
https://note.asca-co.com/n/n0d1153d4a0da
“Connecting the dots (点と点をつなぐ)” by Steve Jobs
その時は気付かなかったけれど、何かのご縁があって与えられた課題をこなしていたことが、振り返れば線となり、大きな成果となって現在に至る。かけがえのない瞬間を、与えられている仕事を一生懸命にこなしていってほしいと思います。
第40回講演者
https://note.asca-co.com/n/n9ee303a882b7
何よりも自分が楽しいと思うことを、まずは精一杯やること。それが後で役に立つかどうかということは考えずに、とにかく今楽しいと思うことをとこ
第39回講演者
https://note.asca-co.com/n/n3d281116f4e9
周りで支え指導してくださる先生方が、私を次なるステージへと連れて行ってくれる。そんな方々がいるからこそ、失敗を恐れずに挑戦することができる。可能な限り大きな課題に立ち向かうことを私は心に留めて生きていく。
第38回講演者
https://note.asca-co.com/n/n72e144d30d52
自分の研究が生かされる場所を追い求め、外の世界へ飛び出していこう。チャレンジせずに後悔するより、チャレンジして後悔するほうがきっといい。私はチャレンジし続ける研究者でいたい。
第37回講演者
https://note.asca-co.com/n/ne6cfae93dfa7
たんぱく質複合体を予測するために構築された、人工知能プログラム AlphaFold Multimer。このAIを利用することで、研究速度が一気に早まった。新技術を巧みに利用できる研究者が新たな時代を築いていく。
第36回講演者
https://note.asca-co.com/n/n00ed42ab5fbf
コロナ・パンデミックにロックダウン、今まで経験しなかった事態における共同研究のスタートだった。それでも研究者同士がつながって、成果を出し合った。議論に議論を重ねて、足りない部分を補い合った3年間 ―― 研究が一つのかたちとなって今ここにある。この経験は必ずや次の難局に立ち向かう糧となる。
第35回講演者
https://note.asca-co.com/n/na9f864208b96
「期待外れ」が生じても、それを乗り越えられる力が私たちには備わっている。ドーパミン神経細胞の役割を最大限に引き出す秘密は、きっと自分が本当に好きだと思うことに出会うこと。運をつかむ力を引き出すこと。人間力を磨くこと。
第34回講演者
https://note.asca-co.com/n/n6b6db29c1512
===============================================
5つの”C”をいつも心に。辞めたいと思ったことは何度もある。それでも前に進むしかないのです。
第33回講演者
https://note.asca-co.com/n/n858a031811cc
自分とは違った専門の人からの意見を取り入れることが、思いもよらない発見になる。人と話すことを恐れずに、粘り強く進んでいこう。
第32回講演者
https://note.asca-co.com/n/n2e0150b2a4e3
世界のトップ研究者というのは案外自分の手の届く場所にいる。それを体感しに海外に出てみよう。Scientistsの舞台は世界なのだから。
第31回講演者
https://note.asca-co.com/n/n91d36124c6c4
医者は目の前の患者さんしか助けられないが、薬学研究者は世界中の患者さんを救うことができるすばらしい仕事である
第30回講演者
https://note.asca-co.com/n/n7dfb413d30ea
Passion(思い)Action(行動)Meet(出会い)思いがあるから行動し、行動することで出会いが生まれる。このつながりが自分を新たなステージへと導いてくれる。Have a passion, take action, and enjoy meeting many people!
第29回講演者
https://note.asca-co.com/n/n5647e3187e2b
好きな研究を続けたくて、博士課程に進学した自分に後悔はない。これからも研究を続けていけるような環境を後輩たちと共に作っていきたい。
第28回講演者
https://note.asca-co.com/n/n6112b17b020f
評価されなかった時代もあった。けれど目の前にある実験結果を信じて研究を続けたからこそ今の自分がある。これからの日本の研究を担う力となる若者たちへ。勇気をもって新たな門をたたいてほしい。
第27回講演者
https://note.asca-co.com/n/n072c02f5dee3
研究者は社会的な生き物であり、研究はビジネスである。一人で悩むことなく、迷った時は仲間に助けを求めることも必要である。研究を楽しんでストレスのない研究生活を送ることが結果的によい研究成果へとつながる。
第26回講演者
https://note.asca-co.com/n/n020447e0aafa
自分が楽しいことを突き進めていってほしい。今、学生は楽しそうじゃない?どうしてだろう。それが不思議。楽しいことが見つかればきっと未来は開ける。
第25回講演者
https://www.asca-co.com/blog/science/entry20221026172150.html
夢を捨てないこと。現実的に生きること。自分が本当に大事だと思う研究はあきらめないで、人にわかりやすく見せる努力をしよう。明日もきちんといきていけるように。ピュアな思いはそのままで。
第24回講演者
https://www.asca-co.com/blog/science/entry20220914134023.html
自分の研究を好きになる。興味があるからもっと研究する。発見は気付かないだけでどこにでも転がっている。Serendipity:セレンディピティ。いつもの心掛けが、想定外の発見を気付ける自分へと導いてくれる。
第22回講演者
https://www.asca-co.com/blog/science/entry20220510181448.html