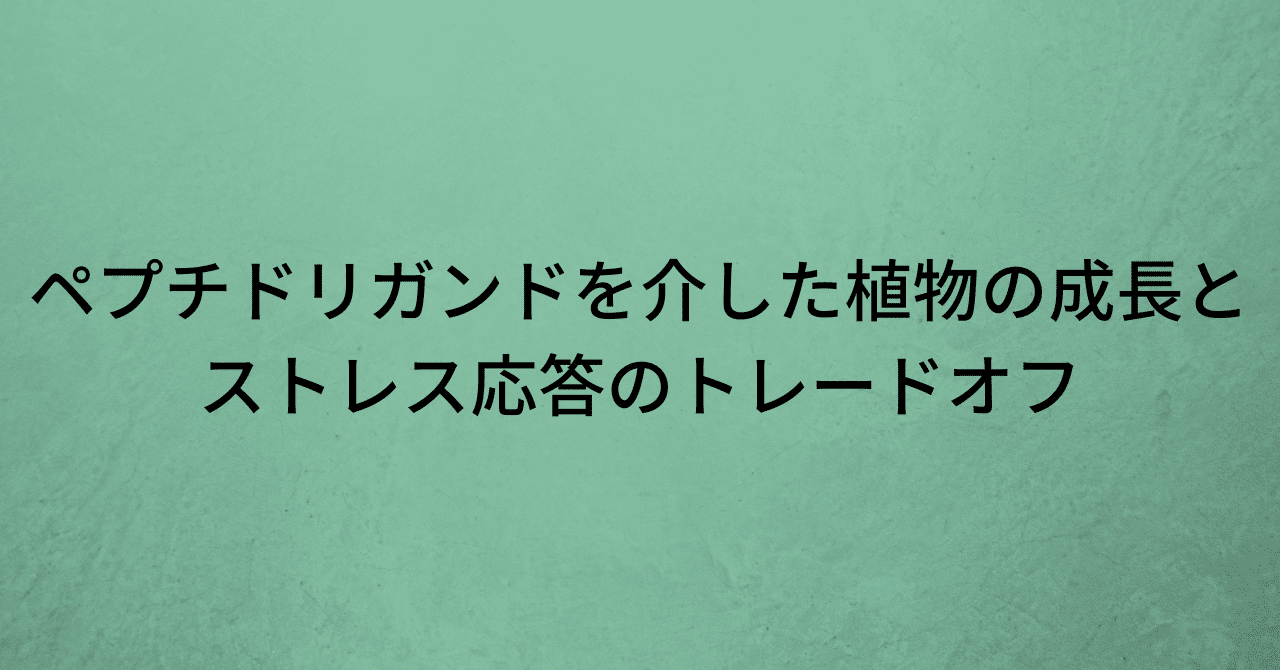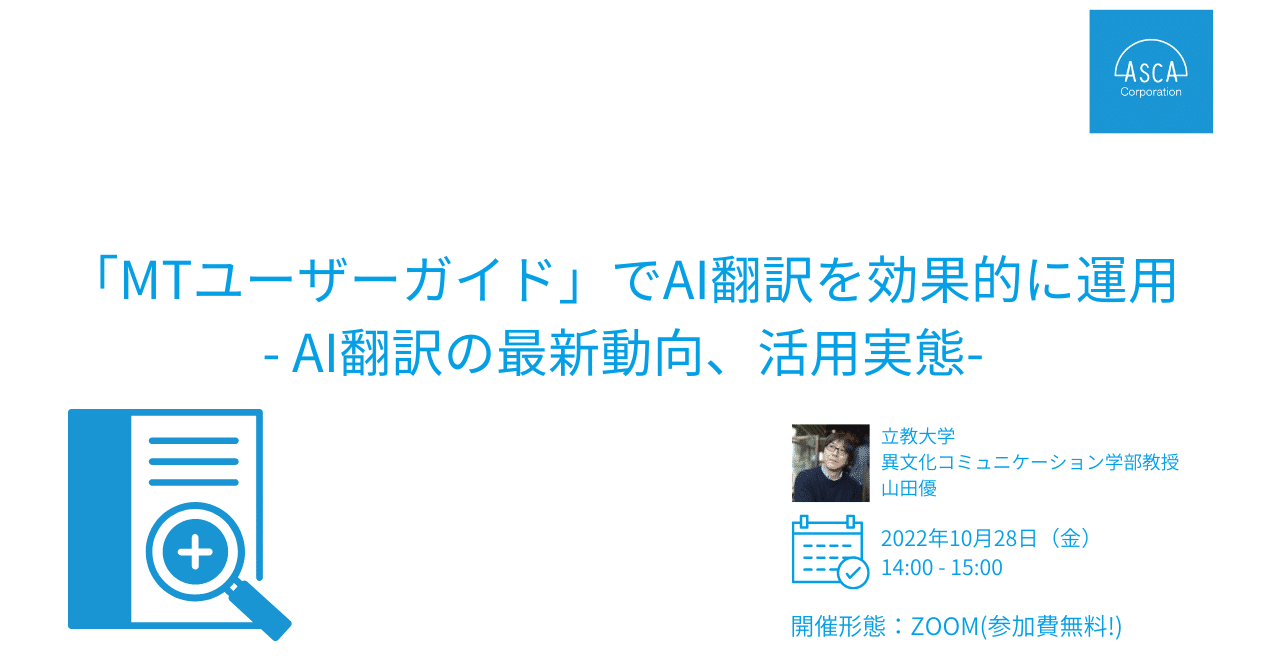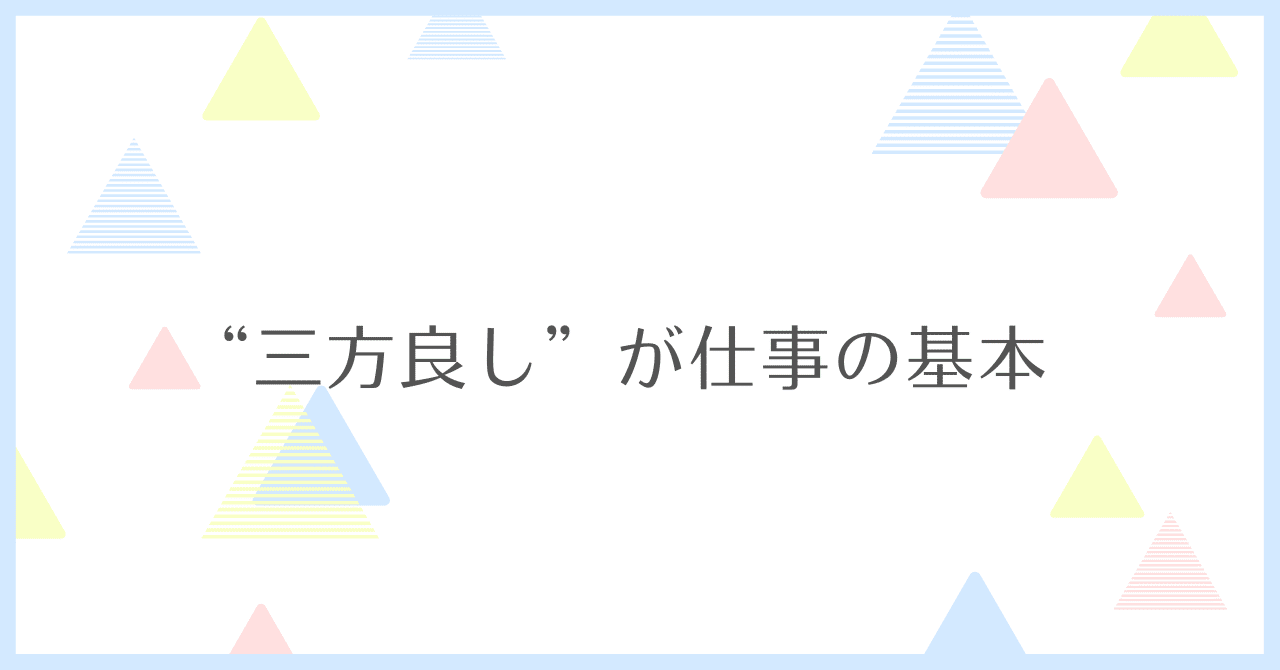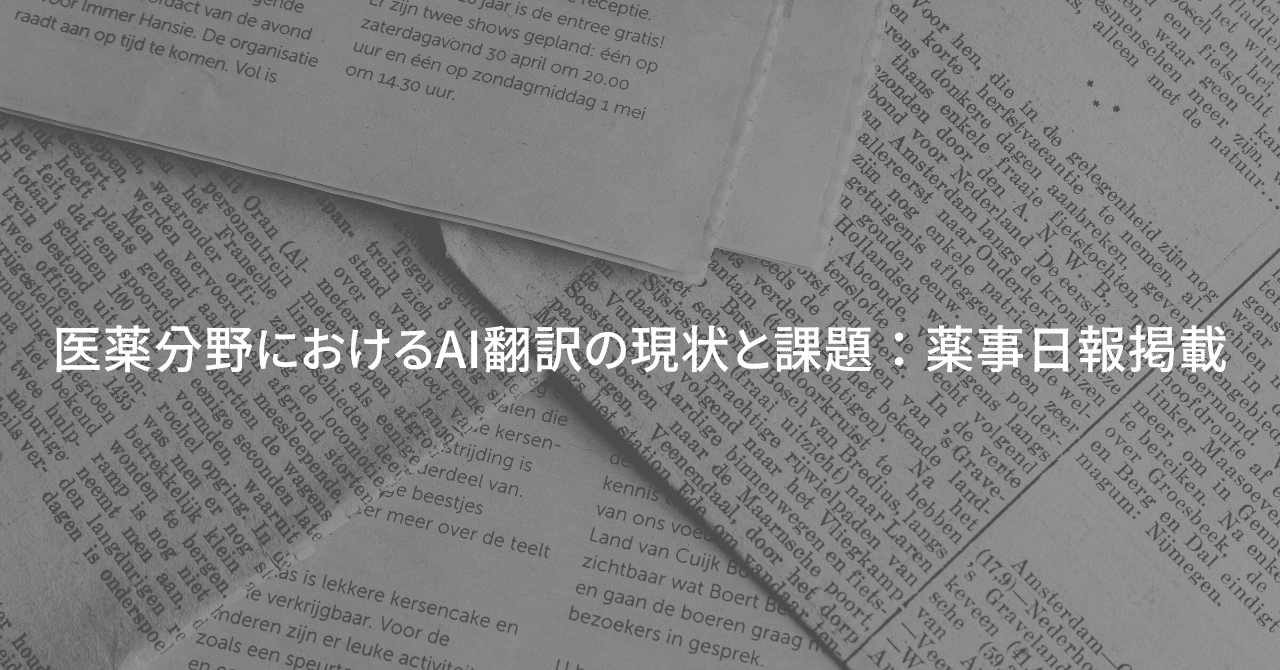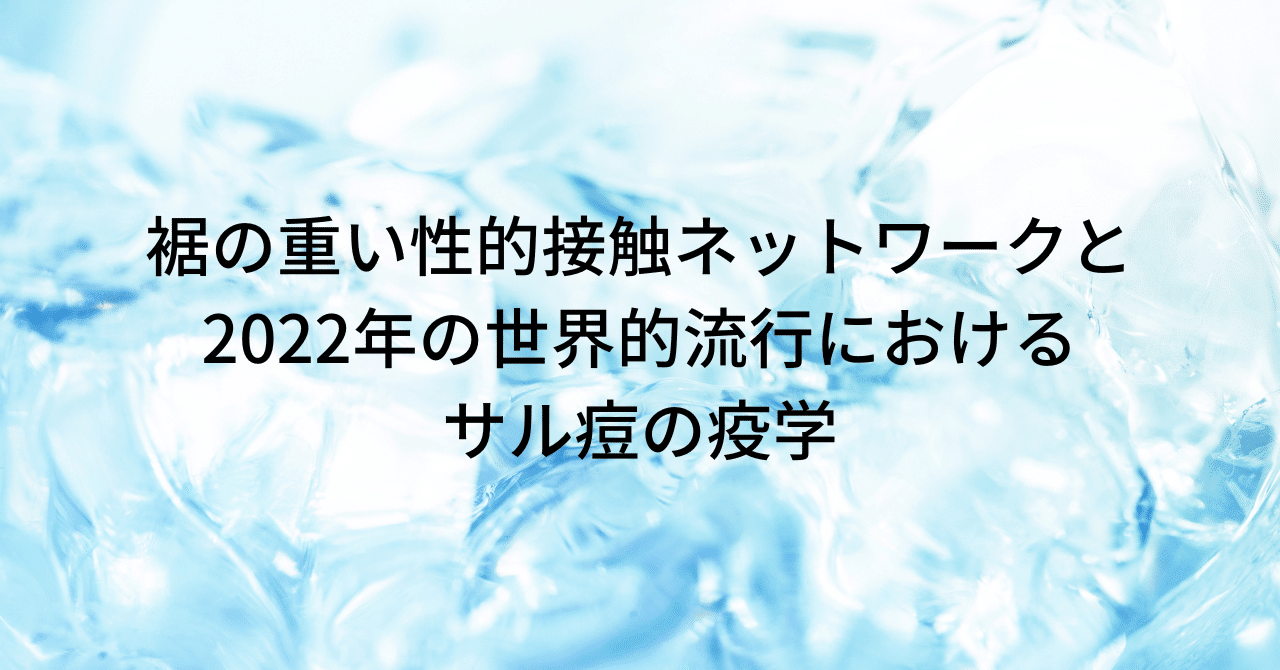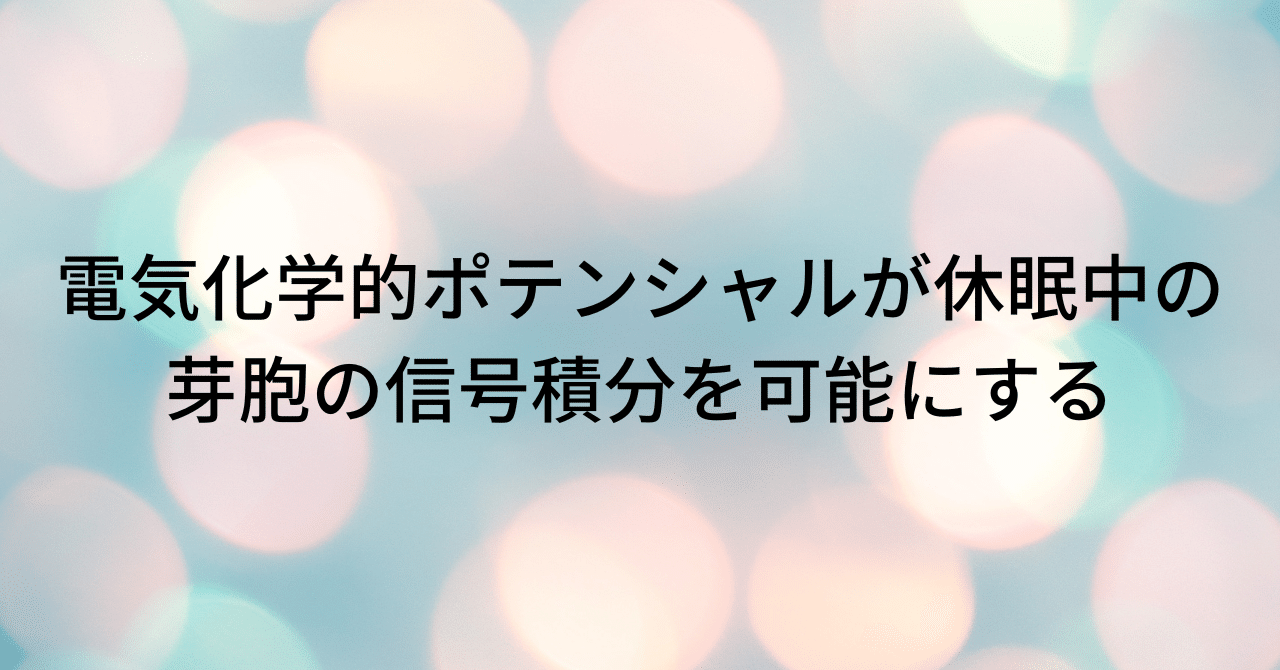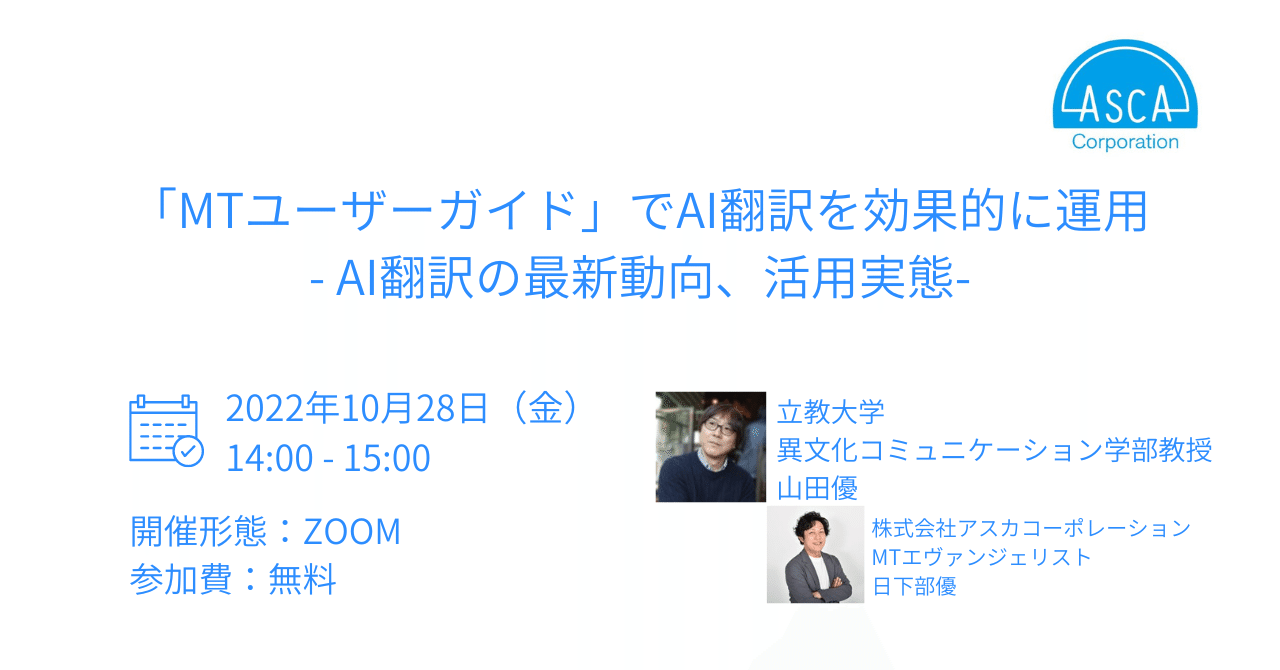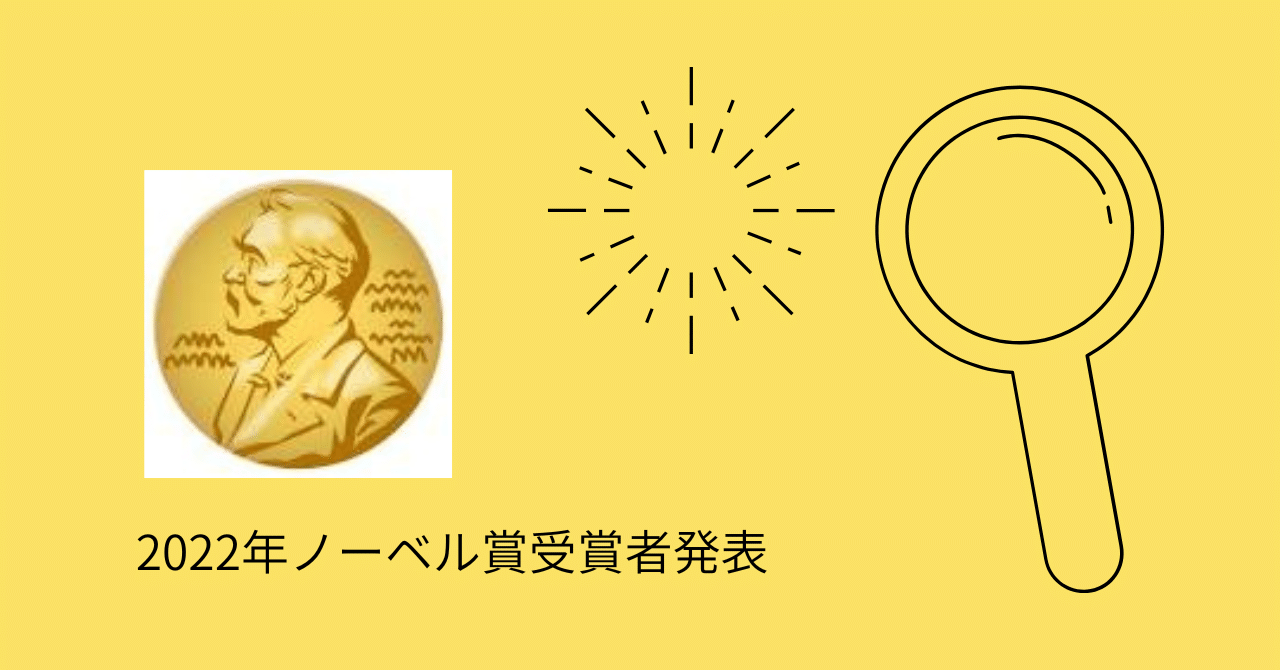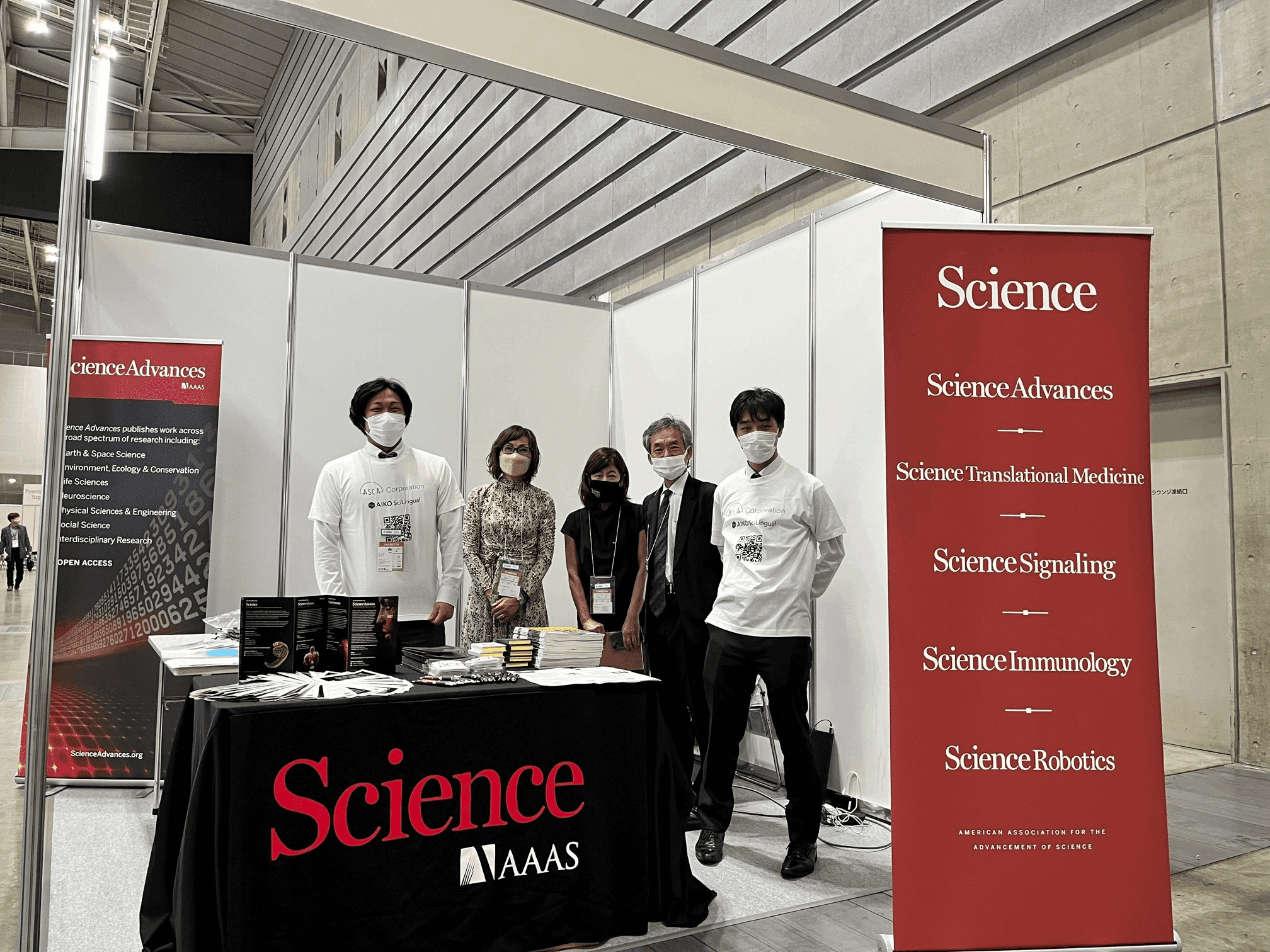(所属、肩書は2022年10月時点のものです)
こんにちは!ASCAコーポレーションで入社日が一番最近の秋山澪です。今回は、私の上司、佐藤直人さんへインタビューをしました。
私が持つ佐藤さんの印象は、「静かに黙々と仕事へ励む男性」です。ASCAで働く部長はどんなひと?というテーマで、インタビューを行いました。
インタビュー後に分かったことは、言葉には出さないけれどクライアントやパートナーさんのことを第一に考え、日々成長するために努力を惜しまない、お仕事に熱心に取り組む真摯な方でしたので、是非最後まで読んでください!
佐藤さんってどんなひと?

佐藤さんを知るなら!ということでまずは基本的なプロフィールをまとめてみました。
<佐藤直人さんプロフィール>
出身地:北海道
血液型:B型
自分目線の性格:負けず嫌い、マイペース、なまけもの
家族や知り合いから言われる性格:優しい、怒らない、話力がある
好きな食べ物:ウニ
嫌いな食べ物:タケノコ、フキ
ASCA入社日:2009年8月11日
秋山が見ている、会社での佐藤さんは、「黙々とお仕事に励んでいる方」ですので、なまけものな性格と聞いたときは意外な回答でした。
佐藤さんの学生時代
秋山)佐藤さんの学生時代は、どんな学生でしたか?
佐藤)小・中学校の頃は、体を動かして遊ぶことばかりしていました。田舎なので、他にやることもなく、将来どうしたいとか何も考えずに、毎日のんびりと過ごしていました。
高校に入ってからは結構勉強をがんばったんですが、なかなか勝てない人がいっぱいいて、そこで負けず嫌いな性格と本気で努力するということを覚えたかなと思います。
大学は、高校でがんばった反動からか、ちゃらちゃらしていましたね(笑)
ASCAへ入社したきっかけ、エピソード
秋山)ASCAへ入社したのは何年で、入社のきっかけは?
佐藤)入社日は2009年8月11日です。ASCAへ入社する前は医療機器の営業をしていて、営業先は主に個人で開業されている医院がメインでした。転職を考えた理由は今後の自分のキャリアを考えたときに個人向けに加えて法人向けの営業のスキルを身に付けたいと思ったからです。
メディカル業界で法人営業ができる会社という条件で、転職先を探していたところ、ASCAを見つけて応募しました。大手の製薬メーカーと取引きがあり、メディカルに特化しているということで、自分の希望にぴったりでした。
ASCAの仕事で大変なことは?
佐藤)ASCAの社員の多くはプロジェクトマネージャー(PM)として、見積から受注、制作(翻訳・チェック等の工程管理)、納品などの業務に携わっていますが、クライアントの希望や案件の内容を翻訳者、チェッカーの皆さんに伝えるというのは何年仕事をしても難しいですね。特に最近は案件の内容が複雑なので、複雑な内容をいかにシンプルにまとめて、わかりやすく伝えるか、すごく頭を使います。また担当する案件は1件2件じゃないですし、社内の業務もありますし、新しい案件も日々入ってくるので、頭を切り替えて整理整頓して仕事をこなしていくのは大変だと思います。
秋山)クライアントが求める質や納期に応えるために、翻訳者さんやチェッカーさんへの依頼は分かりやすく簡潔に伝えるということは、簡単そうに思えて実は難しいですよね
ASCAの仕事で頑張ったことは何ですか?
佐藤)ひとつに絞るのは難しいですが、メディカルライティング業務はターニングポイントになった業務でした。入社して3年目にメディカルライティング業務を立ち上げることになり、最初はクレームばかりで、うまくいかず本当に苦労しました。
今思うと、完全に自分の知識・経験不足だったのですが、この時にどうやったら成功できるのか、元製薬会社の顧問の方に教えてもらったり、社外のセミナーに参加したりして、文書の内容やクライアントが求めていることなどを必死に覚えたことが今の翻訳やメディカルライティング業務に携わるベースになったと思います。
ASCAで目指したいこと
秋山)最後に、これからASCAで目指したいことを教えてください。
佐藤)AI翻訳の台頭により、翻訳業界は過渡期を迎えていると思います。昔、ポケベルが携帯に代わり、携帯がスマホに代わっていったような、そんな転換期に似たようなイメージを持っています。ただ技術の革新はあっても、それを使うのは人なので、これまで培ってきた人の翻訳の技術と、AI翻訳などの新しい技術を組み合わせて、これまで実現できなかったようなソリューションを提案していきたいと考えています。
まとめ
これまので佐藤さんの努力が、今ASCAの部長として反映されていることが、今回のインタビューを通して感じることができました。
クライアントやパートナーさんを第一に考え、苦労したメディカルライティング業務を中心に自身の成長とASCAのサービス向上のために努力を惜しまない姿に、とても感動しました。
私も、製薬会社や翻訳文書など、早く理解できる日がくるように佐藤さん含め多くの先輩方からたくさん吸収し、学び、精進したいと思えたインタビューとなりました。