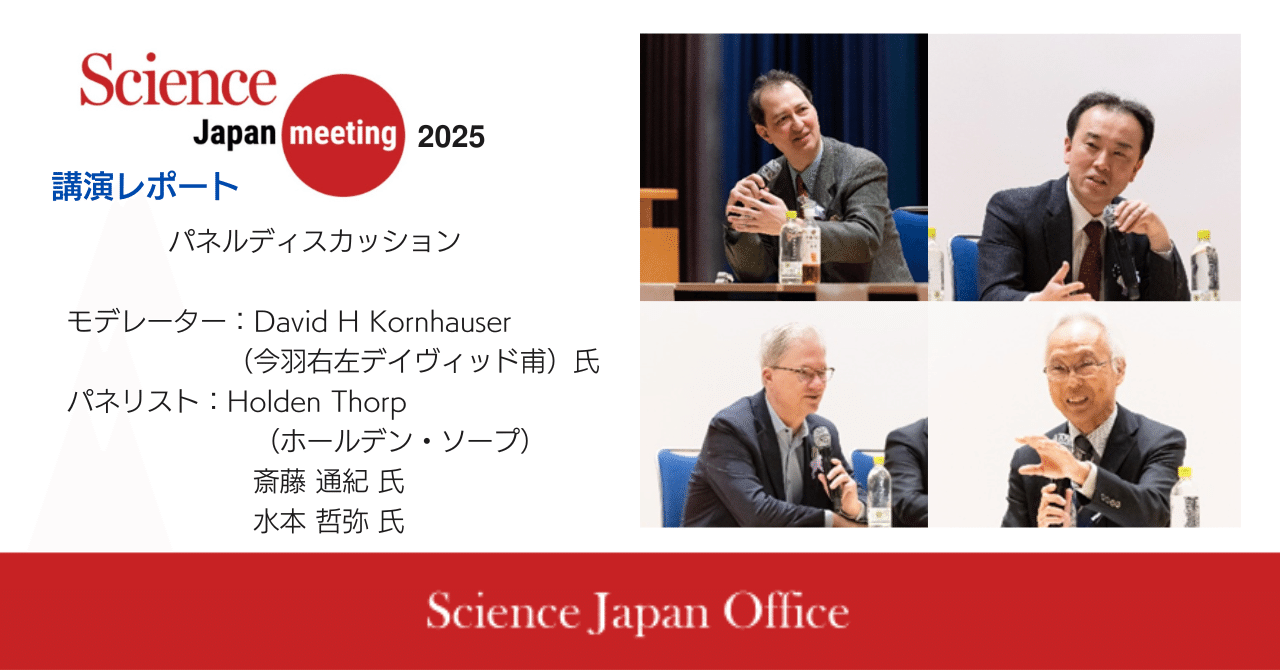
■ 議題:What Can We Do to Enhance Science?(科学を発展させるためにできること)
モデレーター:David H Kornhauser(今羽右左デイヴィッド甫 氏)京都大学 国際広報室 室長
パネリスト:Holden Thorp(ホールデン・ソープ)、水本哲弥氏、斎藤通紀氏
京都大学 Director of Global Communications の今羽右左デイヴィッド甫氏が、「What Can We Do to Enhance Science?(科学を発展させるためにできること)」と題したパネルディスカッションのモデレーターを務めた。パネリストとして参加したのは、Science誌編集長であるホールデン・ソープ、京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)拠点長の斎藤通紀氏、独立行政法人日本学術振興会(JSPS)理事の水本哲弥氏であった。議論は、従来の科学的手法が直面する変革について、特に人工知能(AI)の役割に焦点を当てて行われた。

ソープは、AIが教育や研究に与える影響について、ポジティブな側面とネガティブな側面の両方を指摘した。現在、AIや量子コンピューティングの主要な進展は、学術界ではなく産業界によって推進されていることが多く、その背景には資金力や開発スピードの違いがあると述べた。また、オープンソースの学術モデルが、GoogleのAlphaFoldプロジェクトのように、産業界の透明性向上を促す例もあることを紹介した。

斎藤氏は、自身の研究室におけるAIの活用について言及し、学生やポスドクが計算解析やデータ処理を行う際にAIが有用であると述べた。しかし、AIの限界として、文章が無機質になりがちであり、要約において独自の批判的視点や創造的な洞察が欠ける点を指摘した。斎藤氏は、AIツールを最大限に活用するためには、適切な教育と訓練が不可欠であると強調した。
水本氏は、AIの初期の限界に関するユーモラスな逸話を紹介しつつ、JSPSが研究助成申請の審査においてAIの使用を厳しく制限していることを説明した。これは、未発表の研究データの流出を防ぐためであり、AIを活用する際には機密性と研究の完全性を維持することが重要であると述べた。
また、このパネルディスカッションでは人文・社会科学の未来と自然科学との関係についても議論が行われた。水本氏とソープは、学際的な協力の重要性を強調し、異なる科学分野をつなぐコーディネーターの必要性を指摘した。ソープは、科学の多くの課題は人文・社会科学の理解不足に起因しており、科学の進歩が社会に与える影響を正しく理解するためには、これらの分野の知識が不可欠であると述べた。
全体として、パネリストたちは、科学教育と研究環境においてより柔軟でダイナミックなアプローチが求められることに同意した。ソープは、学生に対して思いやりを持ち、多様なキャリアパスを支援することが、科学者の育成と定着につながると提言した。議論を通じて、科学の未来を発展させるためには、開かれた思考、協力、適応力が不可欠であることが強調された。

コメントを残す