
■ 講演
演題:Ever-Present Challenges of the Research World(研究界における常在する課題)
演者:斎藤通紀氏
京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)拠点長
京都大学高等研究院ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)拠点長の斎藤通紀氏は、講演の中で研究界が直面する継続的な課題について言及した。まず、日本の科学の衰退が懸念されていることに触れ、京都大学で学んだ生命科学者としての自身の見解を述べた。斎藤氏は、京都大学の科学的卓越性の豊かな歴史を振り返り、酸化酵素に関する画期的な研究で知られる早石修教授や、その門下生でありノーベル賞受賞者の本庶佑氏など、影響力のある人物を紹介した。
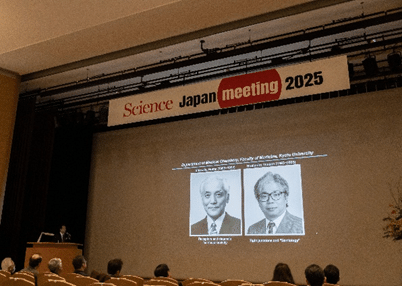
斎藤氏は、科学研究における独創性の重要性を強調し、それは自身の恩師である月田承一郎教授から学んだ原則であると述べた。月田教授は、「構造が機能を決定する」と考え、基礎知識がイノベーションの鍵であると信じていた。斎藤氏は、生殖細胞が、生物の持つ遺伝情報やエピジェネティック情報を次世代に伝える仕組みに強い関心を抱いており、生殖細胞の発生メカニズムの解明に取り組んできた。彼の研究は、マウスモデルを用いて、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から生殖細胞を誘導し、子孫を作成出来ることを証明した。
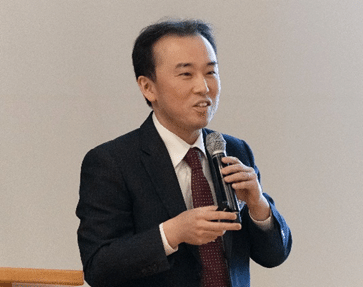
また、独創性、学際的な協力、倫理的配慮がヒト生物学の発展において重要であることを述べた。WPI-ASHBiが国際的かつ学際的な研究を推進し、人間を特徴づける生物学的特性の理解や、ヒト生物学研究における倫理的課題への対応に取り組んでいることを強調した。
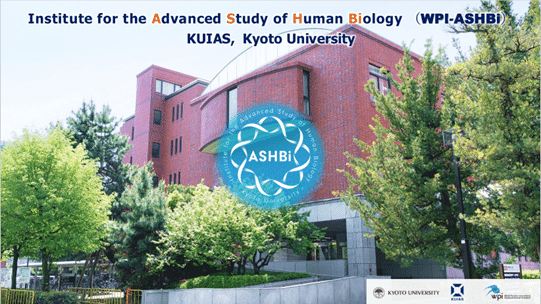
KUIAS, Kyoto University
さらに、ヒトの体外配偶子形成(in vitro gametogenesis)の進展についても言及し、生殖生物学や不妊治療への応用の可能性を示した。一方で、体外で作製された生殖細胞を用いた生殖に関する倫理的課題を認識し、安全性と品質を厳格な科学的評価によって確保することの重要性を強調した。斎藤氏は、科学者と哲学者の間で学際的な対話を促進し、社会がその利用を受け入れる場合に備えて、体外細胞由来の子孫に肯定的な価値を与える枠組みを構築する必要があると提言した。
最後に、日本の科学者の成果を称賛し、研究資金の減少にもかかわらず、日本から生まれる画期的な研究を紹介した。日本の科学競争力を維持するためには、基礎研究への投資を増やすことが不可欠であるとし、学際的な協力を支援する一方で、日本の科学の強みである勤勉さや革新性を維持する必要があると訴えた。
講演の締めくくりとして、若手研究者の給与引き上げや国際共同研究のための行政支援の強化が必要であると述べた。科学の未来に対する楽観的な見方を示し、研究者たちが高い志を持ち続けることを奨励した。
コメントを残す